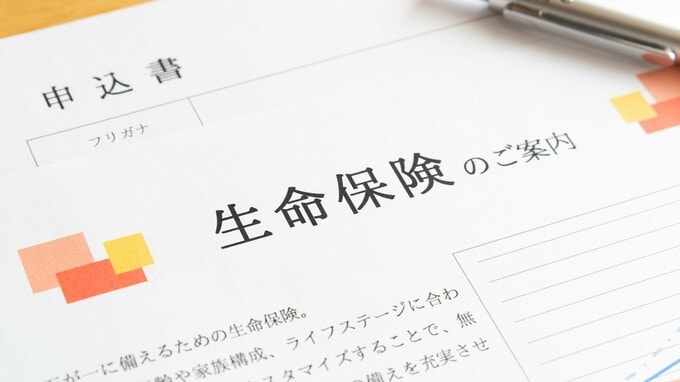二次相続と一次相続の違い
亡父から遺産を引き継いだ母親が亡くなれば、その子どもは相続の手続きを行います。子どもが父親の遺産に続き、母親の遺産も引き継ぐ状態を「二次相続」と呼びます。
一次相続の場合は子どもと母親が法定相続人です。しかし、二次相続では法定相続人が子どものみとなります。
その分、相続税の軽減措置の利用が狭められ、相続税負担が大きくなる可能性もあります。
二次相続で相続税負担が大きくなる理由
二次相続では相続税負担が大きくなる可能性もあり、事前に相続税の軽減措置を取る必要があります。相続税負担が大きくなる理由は次の通りです。
相続税の控除制度の利用が制約される
相続税には基礎控除という税負担の軽減措置があります。こちらの基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」なので、両親とも亡くなり子どもだけが法定相続人になると、その分控除額は小さくなります。
例えば、一次相続の時点で母親と子ども(1人)が法定相続人の場合、
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
相続税の基礎控除額は4,200万円です。
しかし、二次相続の時点で子ども(1人)が法定相続人の場合、
3,000万円+600万円×1人=3,600万円
相続税の基礎控除額は3,600万円となり、600万円もの差が出てしまいます。
また、一次相続の際は「配偶者控除」という極めて大きな相続税の軽減措置も利用できました。
配偶者控除とは、被相続人の配偶者が引き継いだ遺産のうち、課税対象となる額が
・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分相当額
のいずれか多い金額までなら、相続税が非課税となる措置です。この控除制度は配偶者に限定されているため、子どもは利用できません。
子どもが引き継ぐ遺産が大きくなる可能性がある
一次相続では子どもの他に親も法定相続人となっており、その親が配偶者控除を活用し、被相続人の遺産の多くを非課税で引き継いだケースもあるでしょう。
一次相続以後の、次のようなケースでは注意が必要です。
例えば一次相続の法定相続人であった母親が働いていたら、その収入を預金するなどして、母親も資産を形成していた可能性があります。
二次相続では、母親が一次相続で引き継いだ遺産に加え、母親が蓄えてきた資産も合算されるため、相続財産が多くなるケースも想定されます。
相続財産が増えれば、その分、相続税の負担も大きくなるおそれがあります。