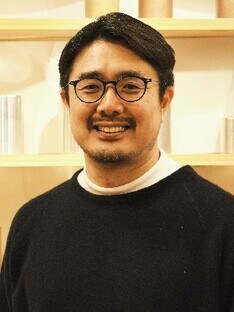開化堂が窮地に陥っていたあの頃
一時期、「苦境にあえぐ町工場」などとメディアで報じられることがありましたが、そういった工場や工房と同じように、開化堂も存続の危機に陥っていた時期がありました。
僕の祖父が当主だった戦後から高度成長期の時代、開化堂はお茶屋さんとお付き合いをし、京都や近畿地方以外にも、年に一度、中国・四国地方に出張していました。
各地のお茶屋さんからその年の注文を聞き、その場で昨年分の代金をいただく、という手形を用いた行商の形で茶筒を販売していたのです。
しかし、当時は機械で大量生産された安価な茶筒が、世界中から日本にドーッと入り始めていた頃です。ましてや、機械製のモノこそがよいとされた時代でしたから、時間もお金もかかる手づくりの製品など、次第に誰も見向きもしなくなってしまいます。
そんな茶筒づくりという商売が苦しくなっていく中にあって、古くからお付き合いのある取引先の方は、「お前のとこはええもんをつくっときなさい。うちが買うたるさかい」と助けてくださいました。
もともとお茶というものの始まりが薬だったこともあって、薬屋さんから暖簾分けもしてもらい、薬も売りながら手づくりの茶筒をこしらえて、露命をつなぐこととなります。
もちろん、当時機械化も考えたと思いますが、プライドなのか、予算の問題なのか、その両方が原因だったのかもしれません。祖父はなんとか手づくり茶筒の開化堂を守ってくれました。
そんな祖父が守り抜いた開化堂でしたが、父の代になり、日本がバブル景気に沸く頃となると、状況の変化にまた直面します。
それまではとにかく安い茶筒が求められてきましたが、好景気も相まってお茶屋さんは質感のよい茶筒を、ギフト需要などに応じて大量にほしがられるようになったのです。
そこで父は、新たな求めに応じて、量をつくれるようにしていきました。
手形や行商での商いが難しくなっていた中にあって、開化堂は取引先を大手のお茶屋さんに絞ることで製造に注力し、工業製品に太刀打ちする方向に舵を切ったのです。
とはいえ、手づくりの製法をやめたわけではありませんから、スピードとコストに勝る工業製品に負けないためには、その差を職人の努力で賄っていくしかありません。