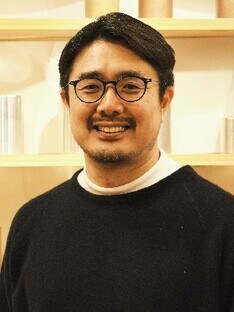バブル崩壊とともに注文の3分の1を失った開化堂
その頃、つくり手は父、母、祖母、1人の職人さん、お手伝いのパートさんで5人くらいだったと思いますが、1日で仕上げる量は、業界用語で「2ハイ」。1ハイが260個ですから、520個という膨大(ぼうだい)な数になります。
それを5人が真夜中までかけて商品を磨き、なんとか翌朝に納品する。それでも、当時、1個当たりの卸値は500円前後でした。
しかも、よそを見れば、大量生産の工場でオートメーション化された機械が、次から次へと均一の製品を流れ作業でつくっているわけです。
ますます機械製は低価格攻勢をかけていましたから、いくらバブルの時代だといっても厳しい戦いを強いられる日々が続いたのでした。
しかし、この職人の努力で張り合えていたのも、バブル期まででした。
バブル崩壊とともにお中元やお歳暮などのギフト需要が減少し、それまで大量に納品を求められた茶筒も必要がなくなっていきます。
そして、ついに、それまで取引させていただいていた三つの大きなお茶屋さんのうち、一つが、「注文をやめる」と言いにこられました。
開化堂の注文の3分の1が一気になくなった瞬間でした。
「哲学」や「空気感」から伝えることへの変化
こうして、私たちは品物をたくさんつくり、大口の取引先に納品するという従来の方法を続けることが難しくなり、それまで「BtoB」がメインだった商いを「BtoC」の形へとシフトしていくこととなりました。
お茶屋さんに茶筒の缶を卸すのではなく、「開化堂」としての名前で、百貨店さんや京都の工房併設の店舗で個人のお客様の前に立つことになったのです。
とはいえ、当然ですが、BtoBだったものをBtoCに切り替えたからといって、急に売れるようになるわけではありません。
最初の頃に大阪の百貨店さんの催事に出た際には、1日の売上が2、3個ということがざらで、大阪のおばちゃんには「これ、何?」「何で高いの?」と言われて、「あんた、もっとまけよしな」と言われてしまう始末でした。
それでも、年数をかけて丁寧に開化堂というものを伝えていった結果、状況がようやく好転していきます。
それは、機能だけではない部分まで、見てもらえるようになったからでした。