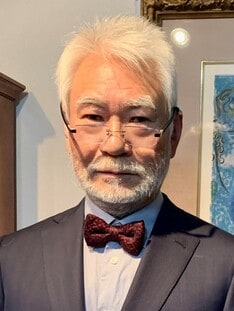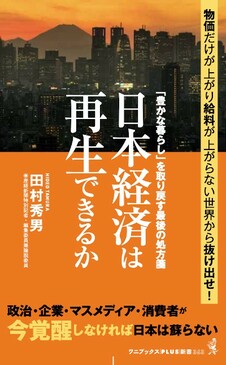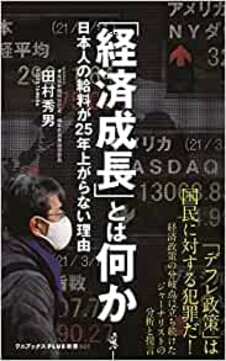ウクライナ戦争で儲けた金融資本
■ウクライナ侵攻で得するのはだれか
ウクライナ侵攻で始まった戦争で、だれが得したのか、儲けたのかといえば、やはり金融資本と答えるしかありません。
わかりやすい例を挙げれば武器です。ウクライナが要請し、それに応えるかたちで米国をはじめとする西側諸国は、ウクライナに武器をどんどん供給しています。もともとウクライナはロシア製の武器を使用していたはずですが、侵攻前から西側諸国の武器への切り替えが進んでおり、侵攻をきっかけに一気に西側諸国製の武器になっています。ウクライナ侵攻の戦闘は、西側諸国製武器とロシア製武器の戦いです。
そうしたウクライナへの武器支援で圧倒的に多いのは米国ですし、NATO参加国が供与しているのも、もともとは米国製がベースになっています。そうしてウクライナに送られた武器は、当初は最先端のものではなく、ちょっと古くなったものでした。
4月26日にドイツ政府は同国の安全保障に関する原則を大きく転換してまで、対空戦車ゲパルトを50両、マルダー装甲歩兵戦闘車80両をウクライナに送ることを決めました。そのどちらも、すでに一線から退いて保管されていた車両です。「在庫一掃」というわけです。米国もNATO参加国も、自らの軍隊の第一線では不要になったものを渡しているところが多分にあります。
戦争というのは、武器の処分という側面が常につきまといます。1990年8月にイラク軍がクウェートに侵攻したのをきっかけに、1991年1月に米軍がサウジアラビアに部隊を展開して他国にも軍の派遣を呼びかけました。その結果、多国籍軍が構成されて、戦争が拡大していきます。湾岸戦争です。この湾岸戦争では大規模なイラクへの空爆が繰り返され、陸戦も広範囲で展開されました。
多くの爆弾や砲弾、銃弾が消費されたわけですが、それも「在庫一掃」と言われたものです。大規模な戦争がなかったために、保管され倉庫に溢れていた在庫を、これを機会にいっせいに処分できたわけです。
兵器は未来永劫に使えるものではありません。最先端のものを備えていなければ、たちまち軍事力で差をつけられることになります。常に最先端のものを開発しつづけなければならないし、開発競争に負けるわけにもいかない。そうなると、必ず在庫が生まれてしまうわけです。
開発を続けるためには、在庫を処分していかなければなりません。それには、戦争こそがチャンスです。ウクライナへの兵器支援は、米国をはじめとする西側諸国にとっては好機だったと言えます。
ウクライナ侵攻での戦闘に直接関わっているわけでもないし、兵器支援をしているわけでもない日本でも、ウクライナ侵攻をきっかけにした防衛意識の高まりを背景に防衛費の大幅増額が論じられています。2022年7月10日投開票の参議院議員選挙で勝利した自民党は、5年以内に防衛費を倍増させる案を明らかにしています。
ウクライナ侵攻によって西側諸国の軍事予算は増え、それによって軍需産業が潤うのは確実です。その西側諸国の兵器需要の恩恵をいちばん受けるのは、なんと言っても米国の軍需産業です。日本も、高い兵器を米国からどんどん買い入れます。軍需産業にしてみればバブルの時代に突入したようなものと言えます。
軍需産業だけが儲かるのかといえば、そんなことはありません。軍需産業に携わる企業が活動して利益を得るためには、その運転資金が必要になります。それを供給する金融の出番です。じつはいちばん儲かるのは、資金を提供する金融資本と言っても間違いないでしょう。
軍需産業が業績を伸ばせば、当然ながら株価も上がっていきます。そこを利用して儲けるのは、金融資本のお家芸です。軍需産業はウクライナ戦争での戦闘が落ち着いていけば需要が減って儲けも少なくなっていくでしょうが、ウクライナ戦争での軍需景気で儲けた金融資本は、その儲けを金融市場に投資することで、さらに多くの利益を稼ぐ可能性があります。
ウクライナでの戦闘が終結したとしても、金融資本だけは変わらず利益を生み出せるわけです。ウクライナでの戦闘でも、その後でも、いちばん得することになるのは金融資本ということになります。