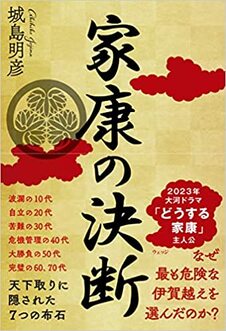寺部城攻めで見せた迅速果敢な決断と行動
■風より疾く、火のように侵略
松平元康(徳川家康)が17歳だったときの初陣「今川軍の寺部城攻め」で見せた迅速果敢な決断と行動は、武田信玄のお株を奪う「風林火山」の旗印そのものといえた。『孫子』(軍争篇)から採った「其の疾<はや>きこと風の如く、其<そ>の徐<しずか>なること林の如く、侵掠<しんりゃく>すること火の如く、動かざること山の如く」だったのである。
疾如風徐如林侵
掠如火不動如山
※武田信玄の軍旗(旗指物)は上記のような2行配列が多い
元康と信玄は敵であり、後述する「三方ヶ原の戦い」では直接対決して雌雄を決することになるが、それでも年齢差を超えて互いに認め合う間柄だったことが各種史料からわかっている。
寺部攻めでは、岡崎城の元康の諸将は、たまりにたまった積年の鬱憤を一気に晴らそうとするかのように初日から獅子奮迅の働きを見せた。なかでも目立ったのは、先頭をきって敵陣に突撃した本多兄弟だった。作左衛門重次と九蔵重玄である。
重次40歳、重玄30代の仲のよい本多兄弟だったが、合戦での命運は別れた。兄重次は敵2騎を討ち取り、自身も深手を負ったものの戦死は免れたが、弟重玄は次から次へと敵兵の首を取った果てに戦死したのである。
重次は、元康の祖父清康や父広忠にも仕えた普代の家臣だったが、当時の岡崎三奉行の特徴をわかりやすく比較した地元の俗謡では「仏高力、鬼作左 、どちへんなしの天野三郎兵衛」(仏のような高力清長、鬼のような本多重次、公平な天野)と歌われた豪傑だった。
『東照宮御実記』(家康から10代家治までの将軍実録)や新井白石の『藩翰譜 』(江戸前期〈1600〜1680〉の337大名の年譜)によると、「高力は温順にして慈悲深く、天野は寛厚にして思慮厚し」で誰の目にも文句なしだったのに対し、本多の奉行起用には「常に傲放にしておもいのままにいひたき事のみいふ事なれば、志慮あるべしとも見えざりし」ということで異論が多かった。
江戸中期の兵法家大道寺友山が書いた家康の事跡集『岩淵夜話』にも、「作左衛門に限り、奉行職など一日も勤まり申す人柄にて無し」とある。ところが、意外や意外、「国務裁判にのぞみ、萬に正しく、果敢明晰なりし」だったことから先の謡の文句となり、世間は「家康公の御ご 眼力の程を感じ奉る」(同)のである。
そのような逸話を持つ本多作左衛門が、どのくらい〝鬼〟だったかというと、のち(1568~1569〈永禄11~12〉年)に家康が今川氏真を滅ぼす「高天神城の戦い」では首18を取り、小田原の役の伊豆韮山城攻め(1590〈天正18〉年3月)では首30 余を取ったのだが、繊細な一面もあり、日本一短い名文として今日でも折に触れて引用される「一筆啓上、お仙泣かすな、馬肥やせ」は作左衛門が妻に宛てた手紙である。
〝鬼作左〟よりもっとすさまじかったのが弟九蔵だ。九蔵の勇猛果敢な戦いぶりは敵兵たちの絶賛の的となり、異例の扱いを受けた。打ち取られた首級を送り返してきたのである。その首を前にして、元康をはじめ、今川軍の将兵たちは13もの刀傷があることを知って驚嘆した。以上は、本筋を離れた〝枝葉〟の話ではある。
合戦では、元康の軍勢が怒涛のように押し寄せ、城主鈴木重辰を本丸へと追い込んだ。その様子を見て、元康は火責めを決断する。「外郭(城の外側の囲い)という外郭に火を放て」と命じたのだ。そこかしこに火の手が上がり、風にあおられて燃えさかった。元康は、大混乱に陥った城内を尻目に、涼しい顔で撤収を命じた。たった1日で寺部城を落としたのである。
2日目は、広瀬城(愛知県豊田市)を攻略した。広瀬城には、矢作川(長野・岐阜・愛知3県を流れて三河湾にそそぐ大川)を挟んで東西2つの城があった。東の広瀬城が本城で、西の広瀬城は「付城」(向かい城、出城、城)、本城を守るために築いた城だった。城主は、東が三宅高清で、西が信長の家臣佐久間信直(信盛の弟)だ。
三宅高清は、南北朝時代にこの城を築いた児島高徳から数えて11代目にあたる。
児島高徳と聞いて、昔の人が反射的に連想したのは、『太平記』が「忠臣」と絶賛した次のエピソードだ。
討幕(鎌倉幕府)に失敗して隠岐送りになった第96代後醍醐天皇を幽閉する屋敷に忍び込んで、庭の桜の幹に「天莫空勾践 時非無范蠡」(天勾践<てんこうせん>を空しゅうすること莫<なか>れ。時に范蠡<はんれい>無きにしもあらず)という漢詩10文字を彫った。「今は難しいけれど、必ずまた助けに参ります」という意味であることを天皇だけがたちどころに理解した。