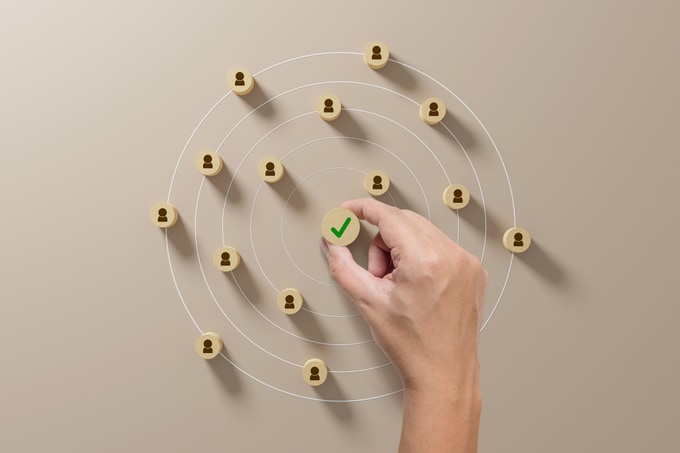1―はじめに
総務省統計局「人口推計」によれば、2021年10月1日現在の日本人人口は1億2,278万人、65歳以上人口が占める高齢化率は29.3%に達している。周知の通り、我が国の人口は2000年代半ばに減少に転じており、総務省統計局「国勢調査」の結果を遡ってみると、2020年の1億2,321万人と同水準であったのは、1990年(1億2,328万人)ごろである。
一方、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(平成29年推計)」によれば、今後も我が国の人口は減少の一途をたどり、2050年代には1億人を割り込むものと予測されているが、人口が1億人を突破したのは1960年代後半と、奇しくも前回の東京オリンピックが開催されていた頃と重なっている。当然のことながら、60年近く前である1960年代後半と2050年、30年ほど前の1990年ごろと現在とでは、人口の規模が似通っていたとしても、社会経済環境をはじめ、人々の生活全般に至るまで、社会のあり様はまったく異なる。
しかし、我々の意識の面では、当時の社会環境に紐づく価値意識が固定観念となって、足元の、あるいは、今後の社会の姿に対する理解の妨げとなっている側面もあるのではないだろうか。
そこで本稿では、こうした時代背景の差異の一端として、人口構成に着目し、総務省統計局「国勢調査」における1965年と1990年、2020年の人口および国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計)」における2030年の推計人口の4時点間を比較してみたい*1。
*1:最新の国勢調査の結果に基づく国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響から、2023年前半の公表を予定されていることから、本稿では参照できない。また、推計の前提となる基礎データと、足元の出生・死亡といった人口動態との間には相応の乖離が生じている可能性もあることから、最新の推計人口が公表されたとしても、推計結果については慎重に見ていく必要があるものと思われる。