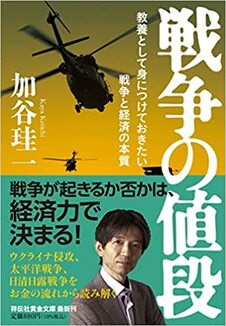個人消費の割合は先進国ほど高くなる
■GDPの中身は、消費・投資・政府支出
経済学の教科書には、GDPについて「1年間に日本国内で生産された最終的な財・サービスの付加価値の総額」と記載されています。財・サービスとは経済学における独特の用語で、財は「形のある商品」のことを指し、サービスは「形のない商品」を指しています。
家電製品や自動車は財ということになりますが、電気やガス、飲食店、介護などはサービスと分類されます。1年間にどれだけの製品やサービスが生み出されたのかを示した数字がGDPというわけです。
これは製品やサービスを提供する側から見た話です。財やサービスを提供した人がいるなら、これを買った人も存在しています。提供する側から見たGDPのことを生産面と呼び、買った側から見たGDPのことを支出面と呼びます。そして最終的にそのお金が誰に渡ったのかという視点で見たものを分配面と呼んでいます。
この3つは同じことを異なる側面から見たものですから、三者の数字は一致するはずです。これをGDPにおける「三面等価」の原則と呼びます。
一般的にGDPについて分析する時には、三つの側面のうち、支出面に着目することがほとんどです。したがって本連載でもGDPについて議論する時には、主に支出面について言及します。
GDPの支出面は大きく分けて3つの項目に分かれます。1つは個人消費(C)、もう1つは設備投資(I)、最後が政府支出(G)です。この3つの項目の金額を足したものが、その国のGDPということになります。
以下の数式は経済学の教科書などに書いてありますから、目にしたことがあるという人も多いでしょう。
Y(GDP)=C+I+G
現実にはこれに貿易収支(NX)がプラスされますので、式はY=C+I+G+NXとなりますが、とりあえずは、CとIとGの3つに着目すれば大丈夫です。
ちなみに、日本における2014年度のGDPは約490兆円でした。このうちもっとも大きな割合を占めるのが個人消費(C)で、全体の約6割、金額にすると290兆円ほどになります。
普段はあまり意識されませんが、経済に占める個人消費の影響力は絶大です。個人消費が活発にならない国は、基本的に強い経済を運営することができません。少し逆説的に聞こえるかもしれませんが、戦争に勝つためには、豊かで活発な消費経済の存在が不可欠なのです。
また、個人消費の割合は豊かな先進国ほど高くなる傾向があり、米国は7割に達します。一方、途上国である中国は4割程度しかありません。次に大きいのが、設備投資(公共投資含む)で金額は100兆円強となっています。
設備投資の中には、企業の生産設備に加え、個人の住宅なども含まれます。途上国はインフラの整備が必須ですから、設備投資の割合が高くなる傾向が見られます。先ほど、中国の消費はGDPの4割程度しかないと書きましたが、中国は消費と同程度をインフラ投資に回しており、設備投資の比率は同じく4割です。
最後は政府支出となっており、こちらも約100兆円です。ざっくりとした形でまとめると、日本はすべての支出のうち、6割を個人が消費し、2割を設備投資に回し、残りの2割を政府が支出するという構図になっています。もし貿易黒字が大きくなれば、NX(貿易収支)の数字が大きくなりますし、貿易赤字であれば、NXはマイナスとなります。
【Jグランドの人気WEBセミナー】
税理士登壇!不動産投資による相続税対策のポイントとは?
<フルローン可>「新築マンション」×「相続税圧縮」を徹底解説