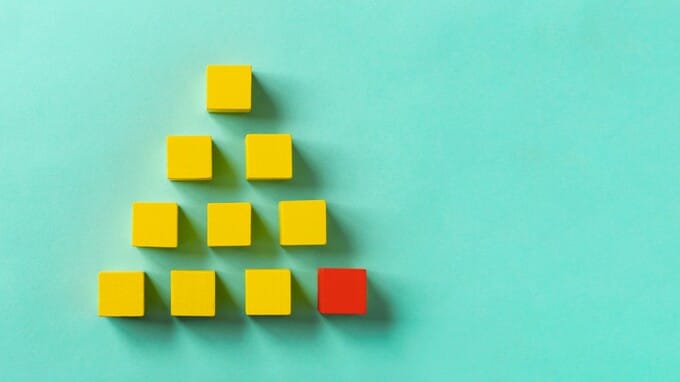【関連記事】4万5000人超…なぜこの経営者団体は会員が増え続けるのか
「脱下請け」「脱一社依存」で会社は伸びる
■下請けいじめは今も存在する
20を超える都道府県の、70人を超える中小企業家同友会の会員に話を聞く機会を得たが、どこにおいてもよく耳にしたことの一つが大企業、大手取引先との軋轢であった。取引の過半を占める地位の優位性を笠に着て、理不尽ともいうべき無理難題を吹きかけられることが多々あるというのだ。ことにすそ野の広い組み立て型の機械・電機・輸送機系産業に多い。
「複数年契約するが、加工賃+材料費を毎年10%ずつ下げてもらいたい」というのはまだまともなほうで、「今月分までは従来通りだが、来月以降は発注量半分、単価は3割カット」などと突然通告され、渋ると「それが嫌なら、契約はこれで打ち切りに」といったケースも珍しくないと聞いた。
要するに「経済の二重構造は解消した」などという一部の楽観的認識は首肯できるものではないし、同友会会員はもちろん、中小企業者の間では「脱下請け・脱一社依存」は依然大きな経営上のテーマであることは間違いない。
古典的な下請けいじめともいうべき事態に直面したのを契機に、慎重に脱下請けへと舵を切り、最終商品メーカーへの道を着々と歩んでいる同友会会員企業がある。表県中小企業家同友会の森合精機がその一つだ。同社は戦後間もない1947年に、現社長の森合政輝氏の父親が神戸市内で創業した鉄工所が前身。ところが56年、13歳のときに父親が急逝、一時的に母親が経営にあたるが、その後64年に法人化したのを機に森合氏が社長に就任している。
森合氏がよく「私は鍛冶屋の親父」と謙遜して語るように、当時は年商5000万円、社員10人ほどのごく小さな町工場にすぎなかった。経営自体も手探りで、その後、一念発起した森合氏が同友会や当時の有名な経営コンサルタント一倉定氏の塾で学んで身に付けていったのである。
その森合氏は同友会仲間の経営者に対して、「下請けというのは、そんな甘いものじゃないですよ」という言葉を吐くことがたびたびある。その言葉は結構とげとげしい。逆に言えば、森合氏はある時期まで、下請けのつらさ、みじめさ、大企業の理不尽さを身に染みて感じていたことを示している。兵庫県には神戸製鋼、川崎重工、三菱重工など大メーカーの主力工場が立地し、下請け企業が広いすそ野を形成している。
森合精機もそのすそ野に連なる一社だったが、森合氏は単純な部品生産では収益が上がらず、従業員に満足な給与も払えないと考え、設備を次第に買い整え、当初のバルブ単品生産からエアバルブの完成品にまで手を広げていく。
下請けからの脱却を図る際、このように経営戦略として割合、無理のないモジュール生産へと進むものだが、しかし森合精機の場合、第一次オイルショック後、親会社とも思い、信頼していた主力取引先から、「おたくとの取引のウエートが大きすぎるから減らす」と突然告げられた。それだけでなく、たまたま不良品が出たこともあって、モジュールから撤退して「元の部品製造に戻れ」とまで命じられる。
このときの危機は新規取引先の開拓などでどうにか乗り切るが、85年以降急激に進んだ円高で、再び森合氏は親会社から煮え湯を飲まされる。「お宅から入れているバルブだけれど、台湾の会社が同じレベルのものを40%安く納められると言ってきている。どうする」と言われたというのだ。
そこで急遽その台湾企業の工場長に面会を求めたところ、現れたのがなんと2年前に親会社から紹介されて、森合精機で学んだ研修生だった。飼い犬に手をかまれたようなものだが、「それが大手のやり口ですよ」と森合氏は言い切る。
■部品メーカーから完成品メーカーへ
これを機に、森合氏は本腰を据えて完成品メーカーに向けて舵を切る。実は森合精機ではすでに油圧機器の自社製造に乗り出しており、その製造ライン用に水洗浄機を自社で開発・製造していた。他社製が性能的に満足できなかったからだ。
そんな折、産業用機器等の洗浄に主として使われていたフロンガスがオゾン層を破壊するというので、96年までに国内はもちろん、先進国でも全廃されることになった。もっともこれを機にすぐに森合精機の水洗浄機が売れだしたわけではない。
「われわれはもともと下請け。ブランド力があるわけではないし、そもそも販売のノウハウがない」
それでも森合氏はトヨタ系各社などに自ら先頭に立って売り込みをかけたが、ほとんど相手にもされなかった。一時は赤字に転落したこともあった。
風向きが変わったのは、「自動車の構造に大きな変化があった」ことだ。マニュアル仕様がオートマチック仕様に変わり、エンジンとモーター併用のハイブリッドシステムが導入され、また車体の電子化、精密化も進み、部品の徹底した洗浄が必要になったのだ。それにつれて森合精機の水洗浄機も売れ行きを伸ばし始め、今では市場の20%超を押さえるトップメーカーである。
先にも記したように、森合精機の2019年1月期の売上高は82億円に達しているが、うち6割は自社ブランド製品が占めている。
M&Aなどにより事業の多角化も積極的に進め、このうち13年に事業譲渡により引き受けたときは8億円ほどにすぎなかった精機事業部などは、19年1月期で24億円まで売り上げを伸ばしている。だが、事業部長は「現在2割余りの自社製品のウエートをもっと上げろと尻を叩かれています」と、森合氏の自社ブランド化に懸けるあくなき意気込みを証言する。
中小企業論の第一人者として知られた中村秀一郎多摩大学名誉学長(故人)は、その著書『21世紀型中小企業』において、かつて中堅企業という概念を提起したが、「中小企業の成長は不可能ないしは例外である」との「通念」の壁に阻まれて、長らく学会ではこの考えは異端視され続けたと記している。
しかし中村氏が指摘するように、中小企業から中堅企業を経て大企業へと成長するのはなにもイノベーションのシーズを有するベンチャー企業に限らない。中小企業としてスタートしても、優れた経営者、優れた技術、優れた商品、優れた販売手法などを手にすれば、ベンチャー企業とスピード面では違っても、成長は可能だ。
製造業においてだが、中小企業が中堅企業へ、そして大企業へと転進していく場合、大きく分けて2つのケースがある。一つは単品の部品メーカーから周辺部品と連結し、独創的なモジュール部品メーカーとして市場のリーダーシップを握ることだ。
当然、そうなると対大企業でも価格決定権を持つことができる。もう一つはその延長で完成品メーカーを目指す道。あるいは部品生産の製造機器を内製化し、そこから独自製品を生み出し完成品メーカーへと進む道もある。前述の森合精機はこの2つの道を複合化して現在に至っていると見ていい。自社の経営資源を生かし隣接分野へ出る、という多角化の原則に合致している。