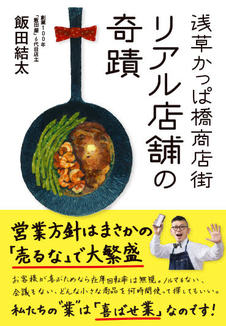【関連記事】集団辞職で天国から地獄へ…従業員から突き付けられた社長失格
大手ができないことが零細企業のチャンス
売れ筋を意識した仕入れをすれば、どこにでもある品揃えの店になります。それがかつての飯田屋でした。
売れ筋を仕入れ、在庫回転率を高めることは大切かもしれません。しかし、それは資金力のある大手企業の戦略です。同じ戦いに挑んでは、飯田屋のような小さな店はあっという間に埋もれてしまいます。わざわざ飯田屋に出向く理由がないからです。
僕たちのような小さな会社が生き残る一つの道、それは大手企業が見向きもしない〝売れな筋〞の魅力を伝えることです。
売れ筋にはわかりやすい魅力があります。そのわかりやすさが万人を惹きつけます。では、売れな筋には魅力がないのでしょうか?
いえ、そんなことはありません。その魅力が少し伝わりにくいだけです。
たとえば、職人が細部まで手をかけた商品は、使ってこそ魅力がわかるものも少なくありません。置いておくだけで勝手に売れる商品ではないため、接客を通して魅力を伝えなければなりません。
それでは時間も手間もかかるため、大手企業では取り扱いたがりません。また、生産量が少ないものも大手チェーンでは展開しにくく仕入れたがりません。
そこに、中小零細企業のチャンスがあるのです。
僕たちのような小さな店の強みは、大手と比べて圧倒的に少ない固定費にあります。だから販売効率に囚われず、お客様とじっくりお話しできます。一人ひとりのお客様にかけられる時間が物理的に長くなります。
もし、僕たちが大手企業と同じような売れ筋しか仕入れなければ、小さくて狭くてアクセスが悪い飯田屋に、お客様がわざわざ来店する理由はなくなります。そこで取り組んだのが、売れな筋を日本でいちばんわかりやすく説明することでした。
さまざまな料理道具を実際に使ってきて、確信したことがあります。「万人に合う道具がないように、すべての人に使いにくい道具もない」という当たり前なことです。
万人が使いやすいよう平均的につくられた道具ではなく、限られた人だけが大満足するような道具が売れな筋にはたくさんあります。そして、多くの人が気づいていないだけで、ものすごい能力を秘めた道具も売れな筋の中にたくさん眠っていたのです。