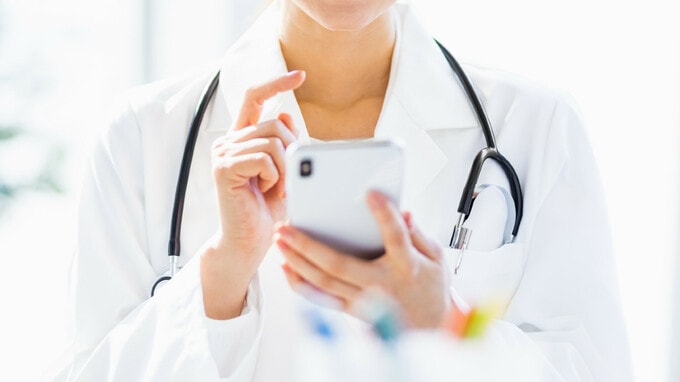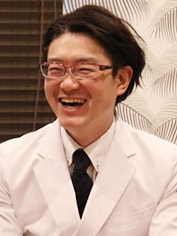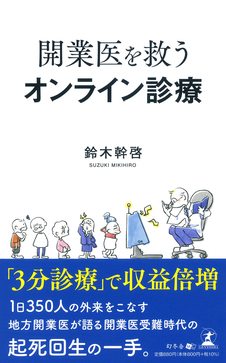三大SNSのユーザー年齢層や「おすすめの用途」は?
■フェイスブック
写真と文章の両方を、大きな制限を受けずに投稿できます。初級者にとって最も取り組みやすいSNSです。SNSで何をしたらいいのか分からない初心者は、まずフェイスブックに挑戦してネットに慣れることをお勧めします。
ただし、若い世代はフェイスブックをそれほど使わないため、中高年向けの情報発信メディアとして使うのがいいでしょう。
なお、投稿する際には文章だけではなく、イメージ写真などで構いませんから画像も付けましょう。そのほうが無機質にならず、読んでもらいやすくなるからです。
■ツイッター
1投稿の最大文字数が140文字しかなく、限られた情報しか載せられません。伝えられることを絞り込んで投稿しなければならないため、初級者にとっては、使いこなしのコツをつかむまで時間がかかるのが普通です。
たくさんの情報量は入れられないので、ユーチューブなどほかのネット媒体にリンクを貼り、そこに飛ばす用途で使うべきでしょう。
■インスタグラム
写真がメインのSNSなので、見栄えのいい、いわゆる「映(ば)える」写真を載せるようにします。比較的若い世代のユーザーが多いため、若い母親がメインターゲットとなる小児科などでは、ぜひ使いこなしたいSNSです。
インスタグラムに長い文章は不向きです。
例えば私は、もともとフェイスブックなどに掲載した文章をインスタグラムに転載することがありますが、このときは元の文章を3つくらいに分けて投稿します。そのほうが読みやすいし、情報も拡散しやすいのです。
医師は、フェイスブックでの情報発信力を高めやすい
フェイスブックで情報発信力を高めるためには、「友達」を増やす努力が欠かせません。そのために有効なのが、さまざまなフェイスブックグループに入会し、そこから友達の輪を広げるやり方です。
例えば私の場合は、「子育て」「保育」といったテーマのグループにたくさん入りました。
そして、グループのメンバーに役立つ情報を書き込んである程度の信頼を獲得し、そのあとで、グループのメンバーに友達申請をしたのです。
フェイスブックでは、見ず知らずの人から友達申請を受け取っても拒否する人が大半です。同じフェイスブックグループに属している人でも、グループ上で何度もコミュニケーションを重ねて信頼されなければ、なかなか友達になってもらえません。ところが、医師という肩書きがあれば信頼度はそれだけで高まり、友達申請は高確率で承認されます。私の場合も、8割以上の人に友達申請を受け入れられています。
「この先生はわかってくれる!」と思わせる文章づくり
なお、フェイスブックなどに文章を書く場合は、このような流れで構成を行うと、より多くの人に納得してもらえます。
(1)問いかけ(問題提起)
(2)自分も一緒(共感)
(3)でも変われた(転機)
(4)こうした(結論)
(5)なぜなら(理由)
(6)あなたも変われる(共感)
(7)ぜひ~してみてください(行動促進)
ここで重要なのが、(2)と(6)の2ステップで読者への共感を示すことです。よく、「SNSは共感のメディア」といわれます。単に有益な情報を提供しても、「あの先生はなんとなく偉そうだから嫌いだ」「理屈は分かるけれど、気持ちでは納得できない」などと受け取られると、決してファンにはなってもらえません。病気などで悩んでいる患者に対し、「この先生は、私のつらい気持ちを分かってくれる!」と思わせることが大切なのです。
SNSは学術論文とは違います。筋が通っていることは必要ですが、それより、読み手の気持ちをつかむことを重視してください。
私はこうした知識を、セールスライティング(商品やサービスを購入してもらうための文章を書くスキル)から学びました。
また、マーケティングの勉強も常にしていますし、3世代が楽しめる高齢者介護施設を作ってその周辺にフードコートなどを整備した際には、飲食業界についても学びました。
経営力を高めたいなら、マーケティングなどの知識も積極的に学ぶべきです。
もちろん、その道の専門家になる必要はありません。医師にとって最も優先すべきなのは、医療の知識や技術を磨くことです。
ただ、余った時間を使ってマーケティングなどの知識を広げていけば、経営には確実にプラスとなります。私は普段、夜9時くらいに眠ります。そして深夜の1~2時には目を覚まし、勉強をするようにしています。
鈴木 幹啓
すずきこどもクリニック院長