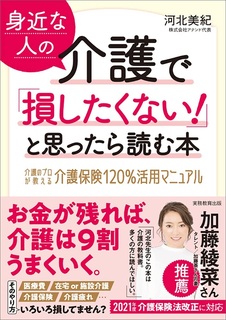「かかりつけ医」に介護度を正しく判定してもらう
介護認定審査会では、保険・医療・福祉に関する学識経験者が話し合って要介護認定の審査を行います。一次判定の結果(訪問調査)と主治医意見書をもとに、対象者の要介護度を公平に審査していきます。
その際、コンピューターでは「要介護1」と出ていた判定が、かかりつけ医による主治医意見書の記述によってひっくり返り、繰り上げられることがあります。
これは「対象者の固有の介護の手間」の情報を、かかりつけ医が提供してくれたことにより、判定よりも介護の手間がかかるとメンバーの過半数が判断したケースです。ですから、ふだんから自分の心身の状態をよく把握してくれる存在を持つことは大切です。
主治医意見書には、生活機能低下が起きている要因が具体的に記載してあります。たとえば、「認知機能の低下が認められ、予防のために週2~3回程度デイサービス利用が望ましい」「ふらつきがあり転倒に注意、見守りが必要である」などです。その他、「火の不始末、暴行、異食行動」などの認知症の周辺症状の情報提供を行います。
<介護認定審査会がチェックするその他のポイント>
①日常生活活動の低下はないか
②外出や社会参加の機会の減少はないか
③家庭内での役割の喪失
など
かかりつけ医がいない方は、地区医師会のウェブサイトに「地域のかかりつけ医療機関」「各科別の医療機関」などの情報が載っており、かかりつけ医を探すことができます。また、地域包括支援センターでも、最寄りの医師を紹介してくれます。