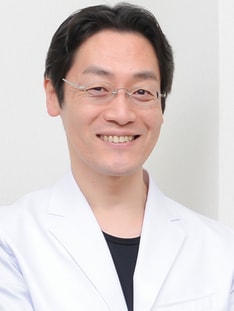待合室が、ますます混み合っていったワケ
医療従事者は、患者から日常的に寄せられる苦情やクレームの数々に悩まされていますが、精神科であれば「あの先生は話を聞いてくれない」「この先生の一言で傷ついた」といった診療内容に関するクレームが多くなります。
もちろんこうした声には真摯に耳を傾けて改善につなげる必要があるのですが、それが延々と続いて、病院スタッフの本来の業務が長時間にわたって中断してしまうことは避けなければなりません。おそらく、「小椋はクレームの原因になりにくい診察をするようだ」と思われたようで、いつのまにか症状の重い患者や対応が難しい患者ばかりを任されるようになったのです。
外来だけでなく病棟でも同様で、非常に治りにくいうつ病やトラウマなどを抱え、薬物療法だけでは改善しない難治患者が多く入院するストレスケア病棟を任されることになりました。
入院患者の回診というと、挨拶に毛が生えた程度で終わるケースもあるでしょうが、こうした患者の回診はその程度で終えられるはずもなく、一人ひとり注意深く症状の変化を聞き取り、丁寧な対応が求められます。
私はこうした姿勢を対人援助職としては当然だと信じ、その信条に従った診療を行い、実際にそれで多くの患者が快方に向かっていくのを見るのは大きなやりがいではありました。
しかしその一方で、ほかの先生方が短時間でさっさと仕事を終わらせているのを見るのは、あまり気分の良いものではありません。しかも、経営側からの私の評価は、こうした先生方と比べて悪いわけではないですが、良くもないのです。
この病院を拠点としながら、週に1度、その病院の系列の精神科クリニックの外来も担当しました。病棟がある大きな病院と異なり、このクリニックでは近隣のエリアで働いている、不眠や軽いうつ症状を訴える患者が中心でした。
症状が軽いからといって、短時間の画一的な診察で症状が改善するわけではないので、軽重にかかわらず、慎重にボトルネックを探していく必要があります。しかし、病棟という安定した収益源をもつ病院とは異なり、街中のクリニックは多くの患者を回転させることでしか収益が上がりません。
どんどん混雑していく待合室の様子に焦りを募らせながらも、限られた時間でなんとかあるべき対人援助を提供しようと努めていました。そうすると、「あのクリニックの小椋という医者はしっかり話を聞いてくれる」といった口コミが出てきていたようで、ますます私の時間は混み合い、病状の重い患者の割合も増えてきました。
時間内でなんとかできる患者もいれば、「もっと診察に時間をかけられれば、良くなるはずなのに」と歯がゆさを感じる患者もいます。不完全燃焼のまま、「続きは次回にしましょう」と終わらせることが多くなりました。そうやって懸命に診察の効率化を心掛けてもなお、最後の患者が帰るのは20時半を回ってしまいます。自分が必要だと考える診療の質を確保しながら、数をこなすことを求められる日々に、ほとほと疲れ切っていました。
**********
こうした経験から小椋氏は、診療がボランティア状態になることなく、経営が圧迫されることもなく、健康保険の枠組みのなかで患者に十分な診療の時間を提供できる、独自の診療モデルを活用したクリニック設立を目指すことになりました。
小椋 哲
医療法人瑞枝会クリニック 院長