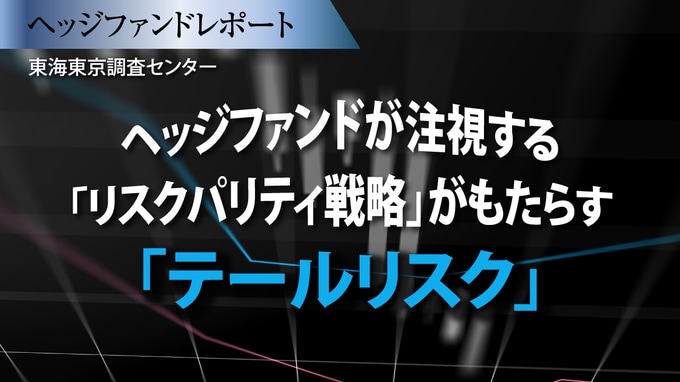\投資対象は株式、債券だけではない!/ 金融資産1億円以上の方向け
「本来あるべきオルタナティブ投資」 >>他、資産運用セミナー多数開催!
リスクパリティ戦略が引き起こす「テールリスク」
リスクパリティ戦略による機械的なハーディング現象が起こるリスクは、以下の3点から推察される。
①リスクパリティ戦略は、分散対象資産でボラティリティが相対的に低い債券のパフォーマンスに依存している点
リスクパリティ戦略は、ポートフォリオの各資産のリスクを均等にする運用戦略であり、リスクの低い資産の配分比率を高くする一方、リスクの高い資産の配分比率を低くするオペレーションを機械的に実施する。
通常、リスクパリティ戦略のポートフォリオではボラティリティの低い債券の割合が株式と比較し高くなる。そのため、シャープレシオの高さは債券のパフォーマンスに大きく左右されるといえる。過去十数年を見ると、リスクパリティ戦略のシャープレシオの高さは、リスクの少ない債券のリターンが優れていた点、つまり概ね安定的にかつ長期的に長期金利が低下し続けていたからこそ、良好な結果がもたらされた可能性が高い。
だからこそ、先行き債券からの良好なシャープレシオが獲得できなくなる局面、たとえば、債券の長期の上昇局面(利回りの低下局面)が終わり、今までの過去のデータにないレベルで短期および長期でボラティリティが下方に高まった(利回りが急上昇した)場合は、リスクパリティ戦略の有用性を大きく低下させてしまうリスクがあろう。
たとえば、FRB(米連邦準備制度理事会)でも制御不能な長期金利の上昇局面、つまり通常、「株式投資家」と比較して冷静で合理的と捉えられることも多い「債券投資家」が不安や恐怖を感じて合理的ではない行動を起こしてしまう局面に該当するかもしれない。
何がカタリスト(きっかけ)になるかわからないし、また「FEDに逆らうな」というウォール街の格言通り、そのような場面は来ないのかもしれないが、ジョージ・ソロスによるポンドの売り崩しが成功したように、万が一、グローバルマクロ型のヘッジファンドが米国長期債の売り崩しに成功するような場面が来るのであれば、リスクパリティ戦略は破壊的なダメージを受ける可能性もあろう。
②債券の利回りが歴史的に低下し、またボラティリティも低下したことによって、リスクパリティ戦略を用いるファンドでレバレッジの活用が増えている点
リスクパリティ戦略を用いるポートフォリオは、債券のウェイトの高さとそのパフォーマンスに依存しがちである。同戦略はそもそもリスクの低い資産である債券の配分比率が高くなる傾向があるため、足元の低金利環境でかつ債券のボラティリティが低下している場合、レバレッジを活用しないとポートフォリオ全体のリスク水準が低くなることが多くなる。
ポートフォリオ全体の目標リスク水準を、たとえば年率標準偏差で10%とか12%とかに設定しているファンドなども多い。そのため、スワップや先物等を活用したレバレッジ取引を活用し、目標リスク水準まで高め、リターンの確保を目指す動きが強まることで債券買い圧力が増加する。
もちろん、レバレッジを活用するため、月間損失率を一定水準(フロア)以内に抑制するようなリスク管理基準を設けることも多い。ただリスク水準の調整は、資産の配分比率を維持したままレバレッジを調整することも多く、債券の急落に伴い、ポートフォリオのリスクが高まればレバレッジの解消を伴って債券の下落圧力を一段ともたらす可能性がある点には留意したい。
③リスクパリティ戦略においては、債券と株式が両方急落する局面になった場合に効果的に対応できる仕組みが弱い点
ボラティリティにおいては、上昇局面と異なり、下落局面や暴落する場合に急上昇する傾向があることが実証されている。株式のボラティリティが大きくなるとリスクパリティ戦略を活用するファンドが株式保有に対するリスクを低下させるため、一斉に売りを出すことになる。
株式市場が急落し、ボラティリティが上昇すると、リスクパリティ戦略ではリスクを均等にするためさらに株式を売却する。その行為がさらに株式市場のボラティリティを高め、リスクパリティ戦略からの一段の売り圧力が生じるといった負のスパイラルに陥る可能性がある。
そのような局面にありながら、上記の①②の要因がさらに伴うと、今までの良好なパフォーマンスを一気に吐き出してしまう可能性も排除できないだろう。金融危機などでも見られたように、パフォーマンスの低下を伴い、ファンドの解約が継続することで一段とリスクパリティ戦略のパフォーマンスを悪化させるスパイラルが働く可能性もあろう。
■まとめ
以上のようなリスクパリティ戦略の機械的なハーディング現象によるテールリスクに備え、インフレ連動債への資産配分を増加させる仕組みや、ハーディング、トレンドフォロー、その他のアノマリー戦略をリスクパリティ戦略に組み合わせてリスク管理を行おうとするヘッジファンドもある。
実際、このようなテールリスクの可能性やインパクトをどのように捉え、また備えとして、どのようなリスク管理手法を組み込んでいるのかを、デューデリジェンス(調査)で押さえておくことも重要だと考える。
中村 貴司
東海東京調査センター
投資戦略部 シニアストラテジスト(オルタナティブ投資戦略担当)
\投資対象は株式、債券だけではない!/ 金融資産1億円以上の方向け
「本来あるべきオルタナティブ投資」 >>他、資産運用セミナー多数開催!
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【2/25開催】
相続や離婚であなたの財産はどうなる?
預貯金、生命保険、株…各種財産の取り扱いと対応策
【2/26開催】
いま「米国プライベートクレジット」市場で何が起きている?
個人投資家が理解すべき“プライベートクレジット投資”の本質
【2/28-3/1開催】
弁護士の視点で解説する
不動産オーナーのための生成AI入門
~「トラブル相談を整理する道具」としての上手な使い方~