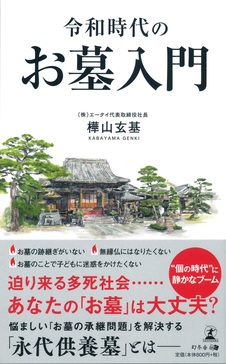「田舎移住ブーム」でも止まらない地方の過疎化
少子化に加え、都市部への人口の集中化に歯止めがかからない現代日本。都市部どころか海外で暮らす人も珍しくはありません。このことは、生まれ育った場所でずっと暮らし、そこで亡くなっていくという人が少なくなっていることを意味します。
昨今はいわゆる「田舎暮らし」の良さが再確認されつつあり、若い人の移住がちょっとしたブームになっている向きもありますが、しかしそれは自然が豊かであるとか、マイペースでのんびり暮らせるといった、より自分のライフスタイルに合った場所を求めてのことであり、自身の出身地に戻ることとは必ずしもイコールになりません。
UターンやIターンも見直されつつあるものの、政治経済の中心はいまだ都市部であることに変わりはなく、そのようにして戻っていく人も全体から見れば、地方の再活性化を大きく盛り上げるまでには至っていないと考えます。

「現在のお墓」を支えるのは高齢者だけ
遠方で生活をしていると、節目節目のお墓参りにも次第に足が遠のいてしまうものです。生まれ故郷に亡くなった親の墓があるが、遠いため墓参りに長いこと行けていないという人もいるのではないでしょうか。たまのお墓参りも長い時間をかけてはるばる、ということになると費用も含め負担となるのは否めず、だんだんお墓参りは面倒なもの、しなくてすむならしたくない、という気持ちになってしまう人もいるかもしれません。
お墓参りができないと次第に、親やご先祖さまを思う気持ちや故郷への愛着も薄れていきやすいものだと私は考えます。故郷のお墓が、人々の心のなかでどんどん遠い存在になってしまうのは寂しいことです。
お墓は一年もすれば周囲に草も生い茂ってきますし、雨風にさらされ汚れも目立ってきます。これではご先祖さまが悲しむことでしょう。
よしんば世話をする人がいるとしても、高齢化がどんどん進んでいるのが実情です。生まれ育った場所に人が戻らないのですから、ずっとそこに住み続けている人がその土地の生活基盤も担っていかなくてはなりません。一昔前であれば若い人に引き継がれていた物事を、高齢者がなんとか、もちこたえているという状況です。しかもその人数も年月の経過とともに減っていく一方です。
いずれその人が亡くなってしまうとお墓を継ぐ人がもういない。ともするとお墓が放置されたままになりかねない。そのような状態が差し迫っているお墓も少なくないのではと懸念しています。
注目のセミナー情報
【国内不動産】2月14日(土)開催
融資の限界を迎えた不動産オーナー必見
“3億円の壁”を突破し、“資産10億円”を目指す!
アパックスホームが提案する「特別提携ローン」活用戦略