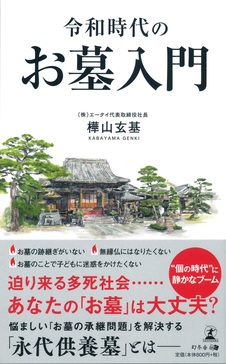お墓をめぐる最大の社会問題は「継ぐ人がいない」こと
現代日本において多くの人が悩む「お墓」の問題。以前の記事『60歳男性、「お前の父さんの遺骨だけど…」親戚の要求に困窮』(関連記事参照)でも解説したように、ここまでいくつか、従来のお墓をめぐる社会的な問題を挙げてきましたが、なかでも最も切羽詰まっているといえるのが承継問題といえるでしょう。
承継問題は大きく二つあります。一つは自分が承継者だが、負担であること、もう一つは、自分は承継者ではないが、次の世代の承継者がいないことです。前者は、自分の入るお墓はあることはあるが、遠方などで不便であるなど、自分が入るまでの管理が難しい問題を抱えています。後者は、現在自分の入るお墓がなく、建てる必要があるものの継ぐ人がいない、あるいは継がせたくない、という問題です。継がせたくない、というのは次世代に負担をかけたくないという気持ちから、というのが大きいでしょう。
それでも、お墓は民法により、あらかじめ、「継続」前提で、先々のことを考えておかなくてはなりません。そして、たとえ「継続」を考えていても、必ずしもそのとおりになるわけではない、というのもお墓の難しい点です。
例えば、今は遠方にいる長男が「いずれはUターンする」と言っていたので地元に墓を建てたが、その後状況が変わり、やっぱり帰らないと言い出した、など、目論見が外れることはよくあります。
家なら、自分たちのあとに住む人がいないのであれば売るなり、更地にすることもできますが、お墓は中にご遺骨があるだけに、家よりもずっと判断が難しくなってしまいます。民法で定められた「承継すべきもの」であるお墓と、従来の墓のあり方がマッチしなくなってきているのです。民法に則って承継しなければならないのに、社会の変化により、それがしにくくなっている人が増えている、というのが最も重大な問題といえます。

大都市圏で年々増える「無縁墓」の数
管理・承継する人がいなくなると、その墓は「無縁墓」となってしまいます。「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」の施行規則第3条に「死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)」と明記されており、法律上は「無縁墳墓」と呼ばれます。
縁故者がいたとしても承継を拒否し、管理費等の支払いがなされなければいずれ無縁墓となります。
無縁墓になるとまず、そのお墓の管理者(お寺や宗教団体、自治体等)によって、承継者候補となる縁故者がいないかどうかの調査がなされます。そのうえで承継者が見つからなかった場合は、原則としてお墓は撤去されます。そしてご遺骨は墓のあったお寺や霊園の合祀墓等へ改葬されます。
墓地の購入にあたっては、その区画の永代使用権も買っていることになっていますが、承継者がいなければその権利も取り消されてしまいます。
しかし実情としては、撤去もされず、荒れたまま放置されてしまうお墓も少なくありません。撤去やご遺骨の合祀墓等への改葬にも費用がかかり、それを誰が負担するか決められなかったり、そこでもめたりすることも多々生じるからです。
なにより、それまでお世話になったお寺や霊園に負担をかけることになります。これでは恩を仇で返すと言われても仕方がありません。
それ以上に、ご先祖さまの供養が途絶えてしまう、ということに対し、無縁墓を抱えているお寺の関係者は胸を痛めています。宗教者である以上、できることなら自分たちで引き続きお墓を守り供養をしていきたい、という気持ちはもちろんあります。しかしいつまでも、費用や手間をかけつづけることは困難といわざるを得ません。
無縁墓の数は年々増加傾向にあります。現在、大都市圏においては「無縁墓がひとつもない」という霊園や墓地は珍しいのではないかと思います。半数近くが無縁墓になっているところもあると聞いています。新しくできたばかりの霊園や墓地には少ないものの、先述のように日本の墓地は1965年頃から増えはじめているので、無縁墓を抱えている墓地のほうが圧倒的に多いと思われます。歴史が古いほど無縁墓も多くなりやすい、といえるでしょう。
先祖の供養ができない罪悪感、迷惑がかかるという不安
無縁墓にするわけにはいかない、ということで多くの方が悩んでいる状況と思われます。とりわけ承継者問題に悩んでいる人は、単にお墓という目に見えるものを管理できないという思いだけではなく、もっと精神的な部分、例えば「先祖の供養ができない」のを苦にしていることが透けてきます。
このままでは供養ができない、ご先祖さまに申し訳ない、かといって改葬し今までのお墓をなくすことにも罪悪感がある、代々守られてきた墓なのに、自分の代でなくしてしまっていいのか、といった悩みです。
自分のあとを継ぐ人がいない場合の承継者問題を抱える人は、先祖の供養というよりは、このままでは自分の墓が無縁墓になり、迷惑をかけてしまうのではないか、といった悩みが主となり、表立っては出てこないものの、やはり供養はしてもらいたい、無縁墓になり放っておかれるのはいや、という気持ちは伝わってきます。
いずれにしても「供養はなんらかの形で継続したい。途切れさせてはいけない」という価値観は、今も昔も変わっていないと私は思います。先に挙げたように無縁墓が増えているとはいえ、本来は、墓の見た目や場所よりも、供養が伴っていることが大事であるというのが、日本に受け継がれている精神、お弔いの心なのではないかと思うのです。
樺山 玄基
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】