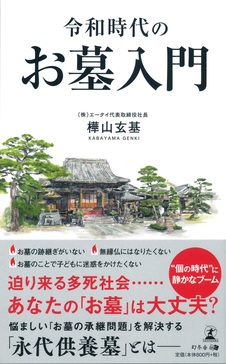「お墓の用意」は家族との相談が必要
新しくお墓を建てようと考えている場合、家でも同じことがいえると思いますが、「どこに建てようか?」と、場所をすぐ決めたくなるものです。
しかし、ここで押さえておきたいのは、従来のお墓は引き継ぐことを前提としているため、「自分だけのものではない」ということです。むしろ、お墓を継ぐ人、承継者の方が後々、管理や供養などの手間がかかるのが現実ですから、承継者を含め家族でよく話し合うことが先決です。
自分の墓だから…と、子どもに黙って墓を決めてしまったものの、あとで大反対されキャンセルせざるを得なくなった、という話はよくあります。
まだ元気なうちに墓のことで家族会議なんて、どうもしにくいなあと気が進まない人もいることでしょう。しかし、お墓は家ほどではないにしても、新たに建てるとなるとかなりの費用がかかることと、代々にわたり何十年と管理していくものですから、家族としっかり話し合っておくことが望ましいでしょう。場合によっては親戚に相談することも必要になります。
一昔前なら、何も言わずとも長男が家もお墓も継ぐのが当たり前、というところも多かったのですが、現代はライフスタイルも多様化し、そうした不文律も通用しにくくなってきました。本人が亡くなってから、きょうだいの誰が継ぐかでもめるケースもありますので、やはり生前に話し合うことが大切です。なお、散骨や手元供養といった、墓を建てない選択肢もあることを付け加えておきます。

「入るための条件」や「購入できるタイミング」は様々
家族の話し合いがスムーズに行われ、承継者も決まったら、墓地やお墓の種類といった情報を集めます。墓地は大きくわけて次の3つのタイプがあります。
〈公営霊園〉
都道府県や市町村といった自治体が管理運営の主体となる墓地のことです。公営なので比較的安価であり、経営的にも安心感があるということで募集がかかると応募が殺到し、抽選になることも珍しくありません。公平性と平等性の観点から、宗旨・宗派はもちろん、石材業者も自由です。
ただし、公営霊園の募集は期間が決められており、かつ応募するにはその自治体に、一定期間以上居住しているなどの申し込み条件のあるところがほとんどです。区画を選べないところも多いので、当選したが場所に不満といったこともあります。なお、公営霊園は原則として遺骨が手元にあることが条件になります。
〈民営霊園〉
財団法人や宗教法人など、民間が管理運営の主体となっている墓地です。居住地など、公営霊園に設けられているような条件は基本的になく、誰でも申し込みができます。また、公営霊園に比べると区画の大きさや建てられる墓の大きさ、デザイン等の自由度が高いといえます。近年では緑地や花壇をあしらった墓地など個性をうちだしている霊園も多くなってきており、購入者が好みに合わせて選びやすくなっています。なお、民営霊園は生前購入も可能です。
〈寺院墓地〉
お寺が管理運営の主体となる墓地です。基本的には葬儀の執り行いをはじめ法要等、供養に関するいっさいの行事をお任せすることを前提として購入します。価格は寺ごとに決めることができるため、お寺による価格差があり、公営や民営霊園に比べ割高になる可能性もあります。
どのタイプの墓地にしても、ただ景色が良いところ、といったロケーションだけを優先させてしまうと、残された家族がお墓参りしにくいなどの問題が起こることがあります。よって墓地をどこにするかも、家族とよく話し合うことが後々のトラブルを回避するためには大切です。
ここは、というところが見つかったら、事前に連絡を入れ見学します。実際にその場所に出向いてみて、利便性などを検討しましょう。
お墓の種類も、「外墓」と呼ばれる従来型の、墓石を建てるタイプの墓もあれば、遺骨を室内に安置する納骨堂もありますし、それぞれ家単位で引き継ぐ家墓、夫婦二人だけで入る夫婦墓など、その墓に誰が入るのかでもお墓の種類は変わってきます。寺院墓地であればその寺院に、墓石を建てる場合は石材店でも相談にのってくれます。
なお、「お墓は生前に建ててもいいのですか?」というご質問をしばしばいただきますが、お墓を建てる時期は基本的にはいつでも問題ありません。ただし前述のとおり、公営霊園など、遺骨がないと建てられない場所もあるので、事前に問い合わせしておくと安心です。
お墓が建つまでには「最低でも2ヵ月程度」必要
従来の一般的な「外墓」の場合は墓石をつくることになります。石材店で、材料となる石の選定から施工まで請け負うことが多く、その石材店も、墓地を決めた際にその霊園や寺院から紹介してもらえることが多いです。
建売と呼ばれる、デザインが統一されあらかじめつくられている墓石もあれば、いちから自分でデザインしてつくる墓石もあり、価格はさまざまですが、100万円前後がいちおうの目安となります。
なお、お墓を注文してから建つまでは、最低2ヵ月程度はかかると考えておくほうが良いでしょう。四十九日までにお墓を建てたい、という方も多いようですが、前述のように急いでことを運ぶと後悔のもとになりやすいといえます。お墓は立地も含め納得いくようじっくり準備し、それまでは家で供養するほうが、トラブルや後悔を回避できるのではと考えます。
樺山 玄基
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】