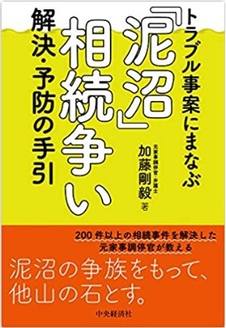「総勢50名近くの相続人」が判明
依頼者は70代の男性でした。大正時代に亡くなった曾祖父名義の土地について、遺産分割を完了したいとのご相談を受け、正式にご依頼を受けました。

なお、相続税の申告には期限があるのですが(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内)、遺産分割自体には期限がないため、このように大正時代に亡くなった曾祖父名義の土地というものも全国にはたくさんあり、遺産分割に期限がないということが、現在社会問題となっている「空き家・空き地問題」の原因の1つになっています。
ところで、受任後に戸籍謄本等を収集・調査したところ、最終的に相続人が全国に50名近くいることが判明し、それらの相続人全員と個別に話し合いをすることは事実上不可能でしたので、相続人全員を相手方として遺産分割調停の申立てをしました。
手続は困難を極めたが…「早期解決」のポイント4つ
調停手続の中で、他の相続人から依頼者に対して「相続分の譲渡」を受けたり、又は「相続分の放棄」をしてもらい、このような相続人を手続から排除してもらうことで、当事者を整理・集約していきました。
しかし、相続人は高齢の方が多く、調停手続の途中で亡くなった方もいらっしゃり、その際には、亡くなった相手方の相続人を新たに相手方に加える必要があったため、相続分の計算も非常に複雑であり、解決には困難を極めました。
そこで、不動産会社に依頼して当該不動産の買い手を探し出し、当該不動産を売却処分したうえで、売却代金から諸経費を控除した残金約2000万円を残された相続人に分配するという内容の「調停に代わる審判」を裁判所に出していただきました。
本件では、まず、①相続人を確定するために漏れなく戸籍謄本等を収集・調査したこと、②相手方が多数にのぼるため、個別に協議することはほぼ不可能であったことから、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしたこと、③知り合いの不動産会社とのネットワークを活かし、当該不動産の買い手を探し出したこと、④当事者の整理・集約を進め、裁判所に「調停に代わる審判」を出してもらったことなどが、相続人の数が極めて多かった割には、受任してから約1年と比較的早期に解決に至ったポイントだったと考えています。
<教訓>
●相続人の調査は入念に。
●不動産会社とのネットワークを活用すべし。
●「調停に代わる審判」を活用すべし。