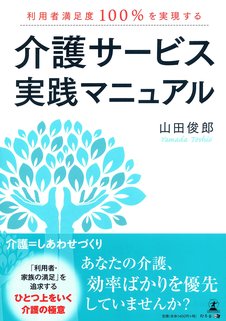「誰も面倒を見てくれない。死ぬしかない」
【地域で孤立する高齢者を支えたい】
■本人の希望・悩みを理解し、見守る環境をつくる
■トラブル時の連絡・対応フローを検討
■地域包括支援センターが中心となって自治体・民生委員と連携をとる
◆地域の支え合う関係から見えてきた落とし穴
地域包括支援センターでは、地域の民生委員や自治会の方々との「顔の見える関係づくり」を心がけています。私の法人のセンターでいえば、健康教室やいきいきサロンなどの開催・協力、地域のお祭りへの参加、各種相談への迅速な対応などです。同様に、警察、病院、消防などの関係機関との関係づくりにも尽力した結果、地域包括支援センターの認知度が高まり、相談窓口としての存在感を発揮しはじめています。
そんな活動の中、地域の中で「孤立」してしまう人が存在するという事実が見えてきました。
それまで、地域で問題行動を起こしたり、問題行動を起こす危険性のある人は、地域で対応しきれずに施設や遠方の家族に預けるというパターンが多くありました。こうした人たちを、地域で支えることが、大きな課題となったのです。
◆孤独のあまり警察に通報し、大騒動に
70歳の女性Kさんも、そのひとりでした。ある日、足首を骨折し、松葉杖を使わなければ身のまわりのことができなくなりました。しかも同居していた娘さんが家を出て行ってしまい、孤独感から精神的に不安定になり「誰も面倒を見てくれない。死ぬしかない」と警察に通報する騒ぎになりました。そこで、警察から私の法人が運営する地域包括支援センターに連絡がきました。

まず私たちがしたことは、Kさんと娘さんへの面談、民生委員や近隣住民、近くの医師への聞き取りでした。