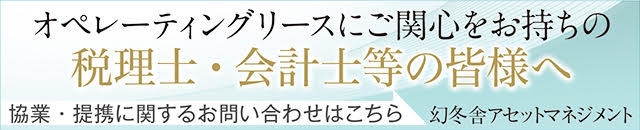\3月20日(金)-22日(日)限定配信/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処法
Q13. なぜ事業法人に日本型オペレーティングリース投資が人気なのか?
A13.投資初期の損益分配によって利益の繰り延べ効果が期待できる、というメリットに魅力を感じることが最大の要因と思われる。以下が投資の仕組みと狙いの概要となる。
「日本型オペレーティングリース」は、オペレーティングリースの仕組みに、日本の商法が規定する「匿名組合」という契約形態を組み合わせて提供される法人向けの投資商品である。
最新情報をお届け!オペリースメルマガ >>登録はコチラ
まず、リース会社やアセットマネジメント会社などがSPC(特別目的会社)を設立し、当該オペレーティングリースの営業者となる。
営業者は、匿名組合の組合員となる法人投資家(以下、投資家)から出資を募り、さらに金融機関(レンダー)からの融資も受けて、借り手(レッシー)に貸与するための物件を購入する。営業者はリース料をレッシーから受け取り、その利益を投資家に分配するという仕組みである。
リース期間満了後、営業者が物件売却によって得た利益についても、出資口数に応じて投資家に分配される。
一方、営業者は、当然、当該オペレーティングリースの費用(貸与する物件の減価償却費及び借入の金利等)も負担する。「日本型オペレーティングリース」での実際の投資家への分配は、収入からその費用を差し引いた「損益」が投資家に分配される。結果的に、投資初期は減価償却負担が大きく、将来の利益を期待しながらも損失が先行する投資となるため、投資家は、投資初期に分配された損失を自社の損益計算書に計上することで利益の繰り延べ効果を得ることができるのである(ここで言う分配とは帳簿上のもので、現金分配は投資期間終了時点での一括清算が一般的)。
【参考】
オペレーティングリースとは?「日本型オペレーティングリース」の仕組み・使い方・メリット
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【2/17開催】日本株長期上昇トレンドの到来!
スパークスだからこそできる「中小型株・超小型株」投資
【2/18開催】
金利上昇、人口減少、税制改正…利回りだけで判断するのは危険
“元メガバンカー×不動産鑑定士”がシミュレーションをもとに考察
「これからの不動産投資」
【2/18開催】
認知症となった80代賃貸不動産オーナー
家族は預金を引き出せず…修繕遅れで物件価値が激減⇒一族全体の問題に!
『高齢化社会における「家族信託」の重要性』とは