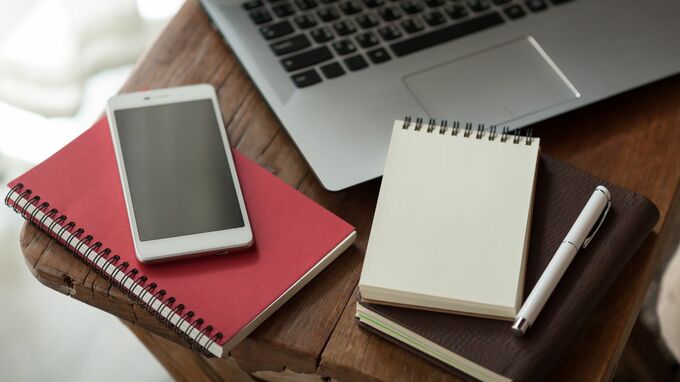I 「企業不祥事における記者会見ガイドライン」を作るのはどうだろうか
執筆者:木目田 裕
1.問題提起・・・「企業不祥事における記者会見ガイドライン」の策定の必要性
(1)昨今、企業不祥事において、記者会見の在り方が取り沙汰されるようになっています。記者会見の在り方については、私も、この危機管理ニューズレターであれば、
・「危機管理及びコンプライアンスにおける本質は「正しいことをしよう」にあり」2024年4月30日号(うち、4.記者会見における「正しいことをしよう」)
・「NGリスト問題を理由とする記者会見の失敗論について」2024年8月28日号
・「NGリスト問題と株主総会」2024年8月30日号
などで取り上げました。
また、最近も「企業不祥事の記者会見等における危機管理」(NBL1280号52頁(2024年))という小論を執筆しています。
私自身、企業不祥事の記者会見には、弁護士として、少なくとも11回、自分で登壇して説明や応答を行っているほか、記者会見の舞台裏での企業へのアドバイス、記者会見シナリオや想定問答レビュー等になると、三桁以上の回数の記者会見に関わってきました。
(2)昨今、企業不祥事における記者会見の在り方に混迷があるように思われます。
例えば、上記「NGリスト問題を理由とする記者会見の失敗論について」でも、報道機関の報道姿勢の問題点と併せて、簡潔に言及しましたが、朝日新聞2023年12月1日朝刊13頁「(耕論)記者会見に求めるもの」(林香里氏、石破茂氏、石戸諭氏(氏名は掲載順))の各コメントでも、記者会見の商業化やショー化の問題などが指摘されています。
そのほか、日本経済新聞2025年2月27日朝刊21頁「大機小機ウェーバーが残した言葉」(三剣)でも、「当日生中継されていた会見を見て驚かされたのは、居丈高な振る舞いで、フジ・メディアHD経営陣をつるし上げる自称ジャーナリストたちだった。ネット上での閲覧数を稼ぐ狙いがあったように思えてならない。・・・(中略)近年、記者会見の劇場化が顕著になっているように見える。そこで批判の目にさらされるのは会見する側だけではない。メディア側も品性と取材力が問われている。」との指摘があります。
さらに、私自身、報道機関の記者の方から「記者会見をやっても聞きたい質問ができない」「記者会見を開催する意味がなくなっている」という声を聞くことがあります。
これは実に憂慮すべき事態です。
インターネットやSNS上の誤情報や誹謗中傷の流布※1が社会問題化しているからこそ、報道機関が社会からの信頼を維持し続けることが重要です。記者会見の混乱や無秩序化を通じて報道機関が社会の信頼を失うことや、報道機関が偏頗な報道や歪めた報道を行うことは、報道機関としての存在意義の自己否定です。
※1 誹謗中傷については、拙稿「誹謗中傷等に対する対策について」本ニューズレター2024年 3月22日号、拙稿「時論 誹謗中傷などの風評 リスクへの対応」金融財政事情 2024年5月21日号 3頁参照。
そこで、まずは、記者会見という場面で、かつ企業不祥事という限定されたものだけでもよいので、「企業不祥事における記者会見ガイドライン」を作り、記者会見のルールないし秩序というものを改めて整理し直すことが大切なのではないか、と思います。
2.ガイドライン上の具体的な論点
「企業不祥事における記者会見ガイドライン」を作る場合、例えば、以下の点が論点になると思います。なお、以下は論点の一部を提示するものであり、ガイドラインの骨子や検討課題を網羅的に示すものではありません。
・企業不祥事において企業が記者会見を行う目的
私の考えでは、顧客、株主、従業員や、さらに広く社会一般に対して、企業が真摯な謝罪と十分な説明を行うことです。
・記者会見の場所・時間等のロジ
時間無制限や極めて長時間の記者会見は、失言探しという不毛なものにしかなりません。自分自身が登壇してきた経験からすれば、人間の注意力や体力の限界、質問の繰り返し・冗長化にかんがみて、適正な会見時間は全体で2時間から3時間程度だと思います。どの記者会見でも、記者会見終了後、企業側が補足説明(記者会見終了後の補足的な記者レクや書面・メールでの質問回答など)を行うことが多いので、万が一、2時間、3時間では企業側の説明が足りない、あるいは分からないということであれば、企業側に補足説明を求めることができます。テレビやインターネットの映像等を通じて企業の謝罪と説明を直接社会に伝えるという観点からも、2時間、3時間程度であれば十分だと思われます。
・企業側説明時間と質疑応答時間の配分
企業側の説明時間は30分程度が適切であり、それ以外の時間は質疑応答に当てるのがよいと思います。
・記者会見の司会者
該当する記者クラブがある場合には、記者クラブの幹事社が司会を行うのがよいと思います。なお、該当する記者クラブがなく、あるいは記者クラブ側が司会を引き受けない場合には、企業の広報担当者または外部ベンダーが司会を行うことになります。企業の広報担当者と外部ベンダーのいずれが司会を行うのが適切かは、個別具体的な事案ごとの判断です。
・企業側の説明姿勢と、報道機関における記者会見準備への配慮
企業側は、真摯に謝罪し、事実関係、原因、被害者救済や原状回復、再発防止策、関係者の責任などを十分に説明すべきです。人の生命身体に対する危険の排除のために直ちに社会に周知する喫緊の必要があるといった特別な事情がある場合を除いて、企業側は、記者クラブ等に記者会見実施を連絡し、適時開示やプレスリリースを行った後(あるいは、会見資料を記者クラブ等に投げ込み(配付)した後)、記者会見開始までの間に、十分な時間的余裕を確保すべきです。というのも、報道機関側も、適時開示等や資料を読み込んで準備をする必要があり、報道機関側において十分な準備ができないと、真摯な謝罪と十分な説明という記者会見の目的を達成できないからです。
・出席者は司会者の司会進行に従うこと
前述した朝日新聞や日経新聞の各記事の指摘を踏まえ、記者会見で、出席者が司会者の指示に従わず不規則発言を繰り返す等といった状況が、テレビやインターネットで生中継・生配信される場合に、こうした映像が、就学児童を含む未成年者の方に与える影響や、社会一般に与える影響について、真剣に検討が必要であると思います。
・記者会見のテレビ中継やインターネットでの配信
記者会見の目的からすれば、原則として、報道機関から、記者会見のテレビ中継やインターネット配信の要請があれば、企業側はこれに応じるべきであると思います。「原則として」という留保を付けたのは、例えば、特定の個人のプライバシーの保護を図る必要がある事案、被害者の二次被害やフラッシュバックに対する配慮が必要な事案、企業の営業秘密や技術上の秘密等の保護を図る必要がある事案、就学児童を含む未成年者でも視聴可能としておくことが適切でない事案などは、生中継や生配信が適切かどうか、個別に検討や対応が必要になると思います。企業側の説明内容及び報道機関側の質問内容でこうした点に配慮することを通じて、なるべく生中継や生配信に対応可能になるようにすることが考えられますが、こうした配慮では問題に対処しきれない場合には、生中継や生配信ではなく、録画した記者会見映像の一部使用にとどめる等の対応が必要になります。
・質問者の指名の在り方
各報道機関に公平に質問の機会を与えるべきであり、そのためには、参加企業数に応じて、1社1問あるいは1社2問に限定し、各報道機関の質問が一回りしたら、二巡目の指名に入ることでよいと思います。
・質問者は質問力を磨くこと
もちろん「私はこう思うが、どうなのか」という質問手法それ自体は適切ですが、記者会見は、企業側に説明させる場なので、「私はこう思うが」の部分は質問に必要な限度にすべきです。「私はこう思うが」があまりに長く、いろいろなご意見を仰ると、これは私の登壇者としての経験からですが、「その方は、一体何を聞きたいのだろうか」と思いながら、登壇者の方で自分の解釈で質問を再構成しながら回答しないといけなくなるため、質問と回答とが、かみ合わなくなる恐れが増大します。また、その分だけ、登壇者が都合の悪い質問についてはすれ違いの回答を行って真摯な説明を回避することも容易になります。
・参加する報道機関は、報道機関としての品位を保ち、関係者のプライバシーや名誉信用に最大限に配慮すること
記者会見は、自己顕示をしたり、視聴率・閲覧回数等を稼ぐ場ではなく、人を誹謗中傷したり、人を傷つける場でもありません。
・記者会見における企業側出席者の範囲
企業側出席者の範囲は、一般論としては、記者会見の目的である謝罪と説明を行うのに適した企業の役職員やその他の関係者となります。「その他の関係者」は、具体的には、第三者委員会その他の調査委員会の調査結果の説明が必要な場合であれば、当該委員会の委員長や委員となります。また、被害者に対する損害賠償や補償など法的問題が関係する場合や企業側の説明を補足するために必要な場合には、企業の役職員とともに、企業の顧問弁護士や危機管理対応を助言している弁護士が出席することがあります。
・記者会見に参加する報道機関関係者の範囲
記者会見の目的にかんがみれば、記者会見の参加者は、報道機関の記者に限定することが適切です。この場合の「報道機関」の範囲については、伝統的なテレビ、新聞等だけでなく、インターネットやSNS上で配信を行っているメディアを含めることが適切です。この点、昨今の誤情報や誹謗中傷の流布をめぐる議論、司会進行に対する協力の必要性といった観点を踏まえると、記者会見参加者の範囲についての議論が必要になっていると思います。
3.結語
「企業不祥事における記者会見ガイドライン」は、報道や取材の自由と密接に関わるため、政府や公的機関が中心になって策定することは、あまり適切ではないように思います。報道機関のほか、経済団体、消費者団体その他の広汎なステークホルダーが集まって、多様な意見を包摂して、適切な記者会見の在り方について社会的な合意形成ができることを期待しています※2。
※2 弊事務所の鈴木悠介弁護士において、こうしたガイドラインの策定のための有識者検討会の立上げに向けて、既に関係各方面と協議しています。なお、本稿は、あくまで筆者の責任において、筆者の見解について執筆しているものです。
以上
Ⅱ 危機管理の切り口から見る近時の裁判例(その7)
執筆者:大賀 朋貴
今回は、大賀朋貴弁護士が、債権譲渡の対価としての金銭の交付が、貸金業法2条1項及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」といいます。)5条3項の「貸付け」に該当するとされた令和5年の最高裁決定(最決令和5年2月20日刑集77巻2号13頁)を取り上げます。
(1)事案の概要等
本件は、被告人が業として行っていた「給料ファクタリング」と称する取引が、貸金業法2条1項及び出資法5条3項の「貸付け」に該当するとされ、被告人が、①登録を受けないで貸金業を営んだとして貸金業法(同法47条2号、11条1項、3条1項)に違反し、②業として金銭の貸付けを行うに当たり、法定の割合を超える利息を受領したとして出資法(同法5条3項後段)に違反したとされた事案です。
被告人が行っていた「給料ファクタリング」は、被告人が、労働者である顧客から、その使用者に対する賃金債権の一部を、額面額から4割程度割り引いた額で譲り受け、同額の金銭(以下「本件交付金」といいます。)を当該債権の対価として顧客に交付するというものでした。なお、当該取引では、契約上、使用者が賃金債権の支払をしない場合に被告人がその支払を負担することはない、つまり、使用者による賃金債権の不払の危険は被告人が負担するとされていたものの、全ての取引において、譲渡された賃金債権の弁済期の前に当該債権の買戻し日が定められ、顧客が希望する場合には、当該賃金債権を買戻し日に額面額で買い戻すことができるとされ、かつ、買戻し日までは、使用者に対する債権譲渡通知は留保することとされていました。
被告人が、本件交付金は債権譲渡の対価であり、顧客に金銭を貸し付けてはいないと主張したことから、本件交付金の交付が貸金業法2条1項及び出資法5条3項の「貸付け」に該当するか否かが争点となりました。
本件の第1審は、本件交付金の交付が貸金業法2条1項及び出資法5条3項の「貸付け」に該当するとして、有罪判決(懲役3年・執行猶予5年及び罰金900万円)を言い渡し、控訴審も第1審を支持していました。
(2)裁判所の判断
裁判所は、上告理由がないとして上告を棄却しつつも、職権で、以下のとおり判示して、本件交付金の交付が貸金業法2条1項及び出資法5条3項の「貸付け」に該当するとの判断を示しました。
本件取引で譲渡されたのは賃金債権であるところ、労働基準法24条1項の趣旨に徴すれば、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同項が適用され、使用者は直接労働者に対して賃金を支払わなければならず、その賃金債権の譲受人は、自ら使用者に対してその支払を求めることは許されない(最高裁昭和40年(オ)第527号同43年3月12日第三小法廷判決・民集22巻3号562頁参照)ことから、被告人は、実際には、債権を買い戻させることなどにより顧客から資金を回収するほかなかったものと認められる。
また、顧客は、賃金債権の譲渡を使用者に知られることのないよう、債権譲渡通知の留保を希望していたものであり、使用者に対する債権譲渡通知を避けるため、事実上、自ら債権を買い戻さざるを得なかったものと認められる。
そうすると、本件取引に基づく金銭の交付は、それが、形式的には、債権譲渡の対価としてされたものであり、また、使用者の不払の危険は被告人が負担するとされていたとしても、実質的には、被告人と顧客の二者間における、返済合意がある金銭の交付と同様の機能を有するものと認められる。
(3)執筆者コメント
特定の金銭の交付が貸金業法2条1項及び出資法5条3項の「貸付け」に該当するかは、行為の形式・外形だけではなく、金銭消費貸借と同様の経済的機能を有する契約に基づく交付であるかを踏まえて、実質的に判断するものと解されているところ※3、本決定は、最高裁として初めて、形式的には債権譲渡の対価としてなされた金銭の交付が「貸付け」に該当するとの判断を示したものとして重要であると思われます。
※3 上柳敏郎・大森泰人編著『逐条解説貸金業法』52 頁
本件決定の調査官解説※4は、債権譲渡の実質があるか否かの判断は、倒産手続に関して問題となる真正売買か否かの判断と共通するとしています。具体的には、①当事者の意図、②法的支配権の移転、③経済的リスクの移転、④被担保債権の存否、⑤対価の相当性、⑥第三者対抗要件の有無などの要素を総合考慮の上、判断されるものとしています。
※4 根崎修一「判解」法曹時報77巻1号314頁
その上で、上記調査官解説は、本決定の2つの理由付けのうち、賃金債権はこれが譲渡された後も労働者に支払がなされなければならないため、「給料ファクタリング」において、被告人は顧客から金銭を回収するほかなかった点(以下、「賃金の直接払い問題」といいます。)について、本決定は、「貸付け」該当性を判断するにあたって、賃金の直接払い問題があるため譲渡債権に係る②法的支配権は完全には被告人に移転しておらず、当該譲渡が担保目的であることを強く推認させることを重視したと考えられるとしています。また、本決定の挙げるもう一つの理由である、顧客は、留保されている債権譲渡通知が使用者になされることを避けるため、事実上、買い戻しをせざるを得なかった点(以下、「使用者への通知問題」といいます。)については、本決定は、使用者への通知問題を踏まえると、顧客が実質的に譲渡債権の買戻義務を負っており、④被担保債権が認められると判断したものと考えられるとしています※5。
※5 なお、本件の「給料ファクタリング」において、使用者の不払の危険を被告人が負担するとされている点については、債権譲渡の対象が 毎月 1 回以上支払う必要がある賃金であり、債権譲渡から弁済期までの期間が通常短期であることや、賃金債権が破産手続においても 厚く保護されていることなどから、実質的にみて、③経済的リスクの移転は「貸付け」該当性判断に直ちに影響を与えるものでないと判断したと考えられるとしています。また、本件において、被告人が額面額から4割程度割り引いた額で賃金債権を譲り受けている点については、手数料として非常に高額であり、⑤対価の相当性を欠き、「貸付け」該当性を基礎付ける要素であると思われるものの、本件では、上記の賃金の直接払い問題及び使用者への通知問題のみから「貸付け」該当性を優に認定できると考えたため、本決定はこの点を判断要素として挙げていないと考えられるとしています。
企業としては、事業者の債権を目的とするファクタリング取引に本決定の射程が及ぶかを懸念されるものと思われますが、本決定が、その主要な理由として、賃金の直接払い問題を挙げていることを踏まえると、本決定の射程は、労働基準法の適用を受けない債権を目的とする事業ファクタリング取引には当然には及ばないものと考えられます。事業ファクタリング取引を行う際に、貸金業法2条1項及び出資法5条3項の「貸付け」に該当するおそれがないかを検討する場合には、上記のとおり、真正売買か否かの判断枠組みが参考になるものと思われます。
以上
Ⅲ 最近の危機管理・コンプライアンスに係るトピックについて
執筆者:木目田 裕、宮本 聡、西田 朝輝、澤井 雅登、寺西 美由輝
危機管理又はコンプライアンスの観点から、重要と思われるトピックを以下のとおり取りまとめましたので、ご参照ください。
なお、個別の案件につきましては、当事務所が関与しているものもありますため、一切掲載を控えさせていただいております。
【2025年4月30日】
消費者庁、景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要を公表
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024740/
2025年4月30日、消費者庁は、2025年3月31日までの国及び都道府県等の景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要を公表しました。本概要には、2024年4月から2025年3月までに国又は都道府県等において法的措置を採った事件の事案概要をまとめた一覧表が付されており、参考になります。
【2025年5月1日】
公正取引委員会、「令和6年度における独占禁止法違反事件の処理状況について」を公表https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250501_kanki.html
公正取引委員会は、2025年5月1日、「令和6年度における独占禁止法違反事件の処理状況について」を公表しました。
本発表によれば、公正取引委員会は、令和6年度においては、独占禁止法違反事件について、延べ61名の事業者に対して、21件の排除措置命令を行いました。排除措置命令21件の内訳は、価格カルテル4件、入札談合6件、受注調整6件、不公正な取引方法5件であり、これら21件の市場規模は、総額921億円超となっています。また、公正取引委員会は、令和6年度においては、延べ33名の事業者に対して、総額37億604万円の課徴金納付命令を行いました。
また、令和6年度においては、109件の課徴金減免(リニエンシー)制度6の利用があり、13件の法的措置において、29の事業者に対して、調査協力減算制度(課徴金減免申請の申請順位に応じた減免率に、課徴金減免申請を行った事業者の事件の真相の解明に資する程度に応じた減算率を付加する制度を指します。)が適用されました。
そのほか、本発表においては、私的独占、価格カルテル等、入札談合、受注調整、事業者団体による構成事業者の機能又は活動の不当な制限、不公正な取引方法といった行為類型ごとに、事業者による違反行為の具体的な内容や、公正取引委員会が行った処分内容が記載されています。
【2025年5月2日】
日本証券業協会、「今般のインターネット取引サービスにおけるフィッシング詐欺等による証券口座への不正アクセス等による対応について(10社申し合わせ)」を公表https://www.jsda.or.jp/about/hatten/inv_alerts/alearts04/higai/index.html
2025年5月2日、日本証券業協会は、大手証券やネット証券の10社と協議を実施し、同年1月以降、第三者が、フィッシング詐欺等による証券口座への不正アクセス等により、顧客の資産を利用して有価証券等の売買等を行い、これにより顧客に被害が発生した場合、各社の約款等の定めに関わらず、一定の被害補償を行う方針とすることを申し合わせた旨、公表しました。
日本証券業協会は、本公表において、証券会社の利用に当たり多要素認証(ワンタイムパスワード等、2要素以上を組み合わせる認証)の設定を行うこと、証券会社のウェブサイトには、公式ウェブサイトをあらかじめブックマークしてアクセスし、メールやSMS(ショートメッセージ)などに表示されたリンクを使用しないことなどの注意喚起も行っています。
【2025年5月16日】
刑事手続をIT化する刑事訴訟法等の改正案が成立https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/meisai/m217080217030.htm
2025年5月16日、刑事事件の捜査や裁判の手続きをIT化する刑事訴訟法などの改正案が参議院本会議で可決、成立しました。主な改正点は以下のとおりです。
▶公判調書等を電磁的記録により作成すること。
▶オンラインによる裁判所に対する申立て等(刑事訴訟法において書面をもってするものとされている申立てであり、例えば勾留決定に対する準抗告申立て等)を可能にすること。
▶捜査機関がオンラインで令状請求を行い、裁判所からオンラインで令状の発付を受け、これを執行することを可能にすること。
▶公判期日において、被告人等を公判廷以外の場所に在席させてビデオリンク方式により行う場合の手続等を定めること。
▶証人が傷病又は心身の障害による同一構内に出頭することが著しく困難な場合や、身体の拘束を受けている証人について、出頭に伴う移動により証人が精神の平穏を著しく害されるおそれがある場合等についても、ビデオリンク方式により証人尋問を実施することができるよう、ビデオリンク方式による証人尋問の範囲を拡大すること。
▶電子化された令状や証拠書類の改ざんを防ぐ手立てとして、電子データの文書偽造罪にあたる公電磁的記録文書等偽造罪などを刑法で新設すること。
▶捜査機関が通信事業者にメール等の電子データを提供させる、電磁的記録提供命令の制度を新設すること。
本改正案の附則においては、一部の規定を除き、2027年3月31日までの間において政令で定める日から、本改正案を施行することが予定されています。
【2025年5月16日】下請法の一部を改正する法律の成立https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250516_toritekiseiritsu.html
2025年5月16日、下請代金支払遅延等防止法(いわゆる「下請法」)及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律が成立しました。
本法律は、下請法に関し、主に以下の改正を行うものです。
(1)協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
▶下請法の対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定を禁止する。
(2)手形払等の禁止
▶下請法の対象取引において、手形払を禁止する。また、その他の支払手段(電子記録債権やファクタリング等)についても、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものは禁止する。
(3)運送委託の対象取引への追加
▶下請法の対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加する。
(4)従業員基準の追加
▶下請法の適用基準に従業員基準を追加する(常時使用する従業員数が300人超の事業者が300人以下の事業者に製造委託等をする場合等7を下請法の対象取引に追加する)。
以上