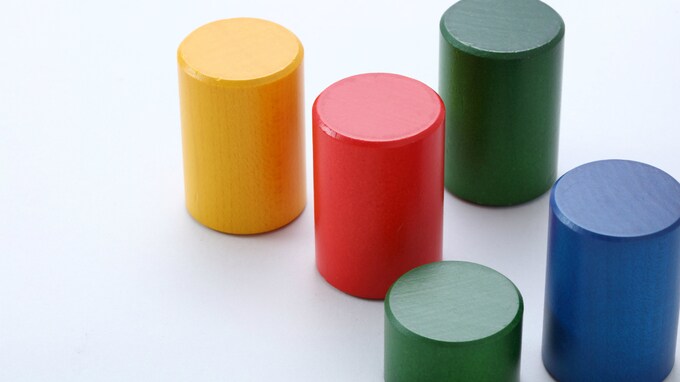「アクティブファンド特集」を見る
投資対象を一つに絞ると価格変動リスクに対応できない
分散効果を得るには、どのような投資手法をとればいいのでしょうか。それを探るために、逆にどうすると「負けやすい」のかを考えてみましょう。
その答えは簡単で、一つの投資対象に絞って投資をすることです。
例えば、すべての資金を日本企業のA社の株式につぎ込むと、A社の株価が上昇すれば資産が増えますが、下落すると資産が減ってしまいます。
では、資金を二分してA社とB社、2社の株式に分けて投資した場合を考えてみましょう。A社・B社の株価がともに上昇すれば資産が増えます。A社が下がっても、B社が上がれば、A社の損失をB社の利益で相殺できるでしょう。ただ株式相場全体が悪化しているような場面ではA社・B社の株がともに値下がりすることも想定できます。
そこで、資金を株式に限定せず国債といった他の資産クラス(投資対象となる資産の種類のこと)にも分散すること、投資先を日本に限定せず、海外の資産クラスにも投資することを思いついたとします。株式が値下がりしている時に、国債が値上がりすればトータルでバランスが取れます。
資産を「守る」「増やす」「次世代に引き継ぐ」
ために必要な「学び」をご提供 >>カメハメハ倶楽部
このように複数の資産クラスに投資をしてリスクを抑えることを「分散投資」と呼び、分散すればするほどリスク低減効果が大きくなります。
「相関係数」を考慮のうえ、資産を分散する
ただし注意しなければならないのは、それぞれの資産クラスの価格変動の相関度合いと価格変動の大きさを理解した上で資産配分を決定しないと分散効果が得られにくいということです。「分散投資しているのに大きく損してしまった」という相談をよく受けますが、こういった方々はたいていこの点を理解せずに投資されています。
相関度合いとは金融の専門用語では「相関係数」と呼ばれ、異なる2つの資産クラスの価格の動きの関係性を数値化したものです。ある資産クラスの価格が上昇(下落)する時、もう1つの資産クラスの価格がどのような動きになるのかを確認するわけです。実際には過去3年など、価格変動の実績値を使って算出しますが、この相関係数は最大値がプラス1.0、最小値がマイナス1.0です。
例えば、資産クラスAとBの過去3年間の日々の価格変動の相関係数が1.0とすると、この2つの資産クラスは価格の上昇と下落が変動の率は異なっても方向は全く同じだったことを示しています。一方、マイナス1.0であったとすると、一方の価格が上がった時に常にもう一方は下落していたというわけです。
相関の低い資産クラスをそれぞれのリスクの影響度と考慮して組み合わせると期待される収益率は変わらずに価格変動特性を安定させることができます。これを我々は「分散マジック」と呼んでいますが、我々だけでなく世界のプロの投資家はこの効果を最大限高めることを目標に運用を行っていると言っても過言ではないでしょう。
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【2/17開催】日本株長期上昇トレンドの到来!
スパークスだからこそできる「中小型株・超小型株」投資
【2/18開催】
金利上昇、人口減少、税制改正…利回りだけで判断するのは危険
“元メガバンカー×不動産鑑定士”がシミュレーションをもとに考察
「これからの不動産投資」
【2/18開催】
認知症となった80代賃貸不動産オーナー
家族は預金を引き出せず…修繕遅れで物件価値が激減⇒一族全体の問題に!
『高齢化社会における「家族信託」の重要性』とは