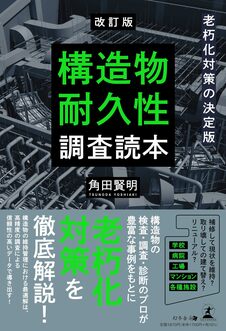建設現場は深刻な技術者不足。業務の効率化が急務に
建設現場での深刻な問題として、技術者不足があります。点検・調査が必要な構造物に対して今後、ますます人手不足の状況になっていきます。
例えば、日本には約73万の橋が存在しています。多くは高度経済成長期に整備されたものであり、2040年には全体の約75%が建設から50年を超えるとされています。5年に一度の定期点検が義務付けられていますが、圧倒的な人手不足が社会インフラの安全確保の問題になっていきます。
そのために調査の効率を上げて、少ない人数で短時間に調査を行う技術を開発する必要があります。
また、2022年度末の時点で、全国の下水管渠の総延長は約49kmに達しています。このうち、標準耐用年数50年を経過した管渠は約3万km(総延長の約7%)であり、今後10年で約9万km(19%)、20年で約20万km(約40%)へと急速に増加すると予測されています。
人手不足を救うのはAIか?効率型ロボット「スカマン」
これらの状況を踏まえ、持続的な下水道機能を確保するためには、計画的な維持管理や改修の実施が必要です。
ますます点検・調査が必要な下水道が増えるなかで、カメラを装備した車両型ロボットを使った調査が進んでいます。このロボットには大きく2つの方式があります。
1つ目はカメラの向きを変えながら、下水道の正面や側面を確認できる「直視・側視式調査」です。
2つ目は、撮影方向は正面のみですが、カメラのレンズを広角にすることで下水管の側面までを写せるようにした「広角展開式カメラ調査」です。直視・側視式調査は横方向の画像も得られますが、カメラの向きを変えるための時間がかかるのでもう1つの方式よりスピードは劣ります。
カメラ付きのロボットを利用して1日に調査可能な距離のことを「日進量」と呼びます。この日進量が直視・側視式調査は約300m、広角展開式カメラ調査は450~600mといわれています。
つまり、作業効率が最大で倍近く変わることになります。私たちが開発した「スマカン」は点検スピードに優れた広角展開式カメラ調査から展開画像を作成します。
そのあとでAI画像診断を組み合わせながら、報告書まで効率的に作成するソフトウェアです。
下水管は膨大な長さがあるにもかかわらず、地中に埋まっており、現状を把握するための調査が困難です。そのようななか各地で下水管の破裂や道路陥没事故が起きています。そのため効率的な方法で多くの下水管を調査することが大事だと思います。その点において「スマカン」の作業パフォーマンスは期待できます。
さらに重要なのは、報告書を作成するプロセスです。実は調査が効率的に行われても、技術者が報告書を作成するためにかなりの時間がかかっています。現場ではデータがたくさんあってもまとめきれない事態が起こっているのです。
これを改善するためには、報告書作成の可能な限りの自動化、そしてソフトが使いやすいものであることが欠かせません。スマカンは、現場の技術者の意見を聞き、使いやすさを重視したうえでAI画像診断によりできるだけ自動化するように配慮しています。
1例では今まで10時間かかっていた報告書作成が5時間で終わるまでに効率化されました。