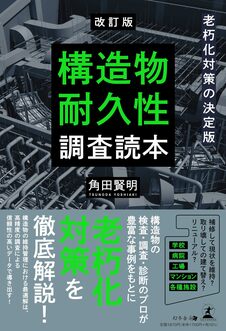耐久性調査はこれからどうなるのか
ここで私たちが行っている建物の検査や調査の仕事が、未来に向けてどのように変わっていくのか、そのための調査に関わる技術者の課題は何なのか、展望をお伝えしたいと思います。
私たちが受けた事例のなかでもある老朽化した大学の建物は、予算10億円のリニューアル工事を予定していましたが、建物の寿命が20年はないとリニューアルの意味がないため、寿命を調べる必要がありました。
実際に調査の結果、20年以上の寿命があることが示せ、リニューアルが進められました。
一方で、ある河川沿いの施設は築80年は経っていましたが、まだ使い続けたいというのが耐久性調査を依頼された理由です。調べてみると耐用年数は5年程度しかありませんでした。私たちの調査はそれで終わりましたが、のちに状況を確認すると、まだその建物は使い続けているとのことでした。
そのため、私たちが耐久性を適切に評価したとしても、それは気休めにしかならないのではないかという考え方もあると思います。
現実的には人が寿命を迎えるように、崩れ落ちて寿命を迎える建物というものはほぼありません。その前に取り壊すという決定がされます。
特に日本では、建物よりも土地が重視される文化が根強く、建物は経年劣化とともにどんどん価値が下がっていきます。物件が新しい建物を建てるための土地として見られ、建物を取り壊す費用分がマイナスの価値と見られることも多いのです。
また建築物によっては、改修が難しいこともあります。そのため、新しく建てるほうが経済的に合理的と見なされることもしばしばあります。
さらに、都市部では土地の容積率が変更されることが建て替えを促したり、新築が好まれる文化もあったりします。このように、建物の寿命はその本質的な寿命よりも、所有者の意思や、経済的、環境的な要因および用途や設備などの機能上の理由に大きく左右されます。
ここで大事なことはその判断基準です。建て直すにしろ、リニューアル工事をするにしろ、数十億円の投資についての意思判断になってきます。
しかし、私たちの提供する耐久性調査がなければ、その判断基準は「もう50年経ってしまった」という感覚的なものでしかありません。そんな現状に対して、工学的調査で建物の寿命を評価して、意思決定基準として使えることが、耐久性調査の価値ではないかと考えています。
耐久性調査におけるニーズの広がり
現在の耐久性調査はゼネコンや行政機関などから依頼される場合が多いです。この場合、建物を利用するエンドユーザーとの間にゼネコンなどが間に入って進めていくわけです。こうした仕事の形は将来にも残っていくと思います。
また工場を所有するクライアントが、どのように建物を拡張していくか、メンテナンスしていくかという課題に応えるようなニーズも広がっています。
さらに、不動産業界や金融業界における調査ニーズに応えることも重要だと思っています。不動産業界や金融業界にとって建物は、買い主と売り主がいる流動資産という見方もあります。違法な増改築の有無やアスベストの使用の有無、こういった潜在的なリスクを把握し、取引するのです。
このような不動産の流通過程におけるニーズに応えるサービス強化も必要であると考えています。遵法性調査や老朽化調査など、買い主と売り主が安心して取引できるデータを提供する需要は今後増えていくはずです。
金融機関、投資ファンド、不動産デベロッパー、不動産仲介業といった幅広い業種が耐久性調査を求めているのです。
この場合、現在のクライアントから変わることになるため、クライアントの使う業界用語なども学ばなければなりません。
例えば、経済合理性や投資のリターン(ROE)関連の数値を学んだり、それを説明するためのデータを取る技術も求められたりすることになります。「この修繕にはいくらかかるのか」というような、コストに関する具体的な質問に対応できるよう、私たちも成長していかなければなりません。
さらに調査はコンサルティングの領域にも広がっていくと考えています。
もちろん、これは自分たちだけでできることではありません。外から、私たちにない知見を持った人材を迎えることが必要となることもあります。
そのため、私は金融業や不動産業の経験のある人材を仲間に加える採用活動も続けています。
こうした活動を進めることで、異業種のクライアントに対しても、共通言語でコミュニケーションを取ることができるように変わっていく将来も見据えていかなくてはなりません。
人に伝えるための技術これまでの耐久性調査は、ゼネコンや行政機関などの専門家に対して提供してきたものでした。
しかし、このように建物の所有者や不動産業の方々にもクライアントが広がっていくことを考えるといくつかの課題があります。まずは知識の専門性が高いことです。