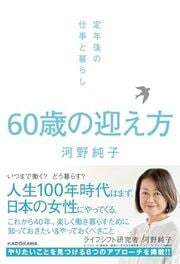60歳女性を取り巻く「雇われる働き方」の厳しい現実
会社員であっても働く喜びは感じられますし、政府の要請や昨今の労働力不足を背景に、定年を廃止する企業も出てきてはいます。ただ聞こえてくるのは、60歳前後の女性を取り巻く雇用環境の厳しい実態です。
ここで少し「雇われる働き方」のいまを俯瞰しておきましょう。
企業の定年は、年金支給年齢の引き上げと足並みをそろえる形で政策的に延長されてきました。厚生年金制度が発足した1944年の年金支給開始年齢は55歳。これは当時、多くの企業が男性の定年を55歳としていたからです。
その後、1954年の改正で男性の年金支給開始年齢が60歳に、1985年の改正で女性も60歳に引き上げになります。男女ともに65歳での支給開始が決定したのが2000年のことです。
一方で企業の定年は高年齢者雇用安定法によって1998年に男女問わず60歳以上に義務化されます。その後、2013年に65歳までの雇用確保措置が義務化、2021年に70歳までの就業機会確保措置が努力義務化されています。
具体的には、いま企業には65歳までの雇用確保のために、①定年制の廃止、②定年の引き上げ、③継続雇用制度の導入のいずれかの措置を講じることが義務付けられています。 加えて70歳までの就業機会の確保のために、上記の3施策に加えて、④業務委託契約を締結する制度の導入、⑤社会貢献事業に従事できる制度の導入を講じる努力が求められています。
2021年の法改正は、人件費や組織活性の観点から企業にこれ以上の雇用措置を求めることは難しいため、「雇われない働き方」を支援する要素が加わり、時代の変化を感じさせるものでした。
では実際に企業はどんな対策を講じているのかというと、定年制を廃止した企業はわずか3.9%。定年が70歳以上という企業は2.3%、65歳が23.5%。66.4%の企業が定年は60歳のままで、継続雇用によって65歳までの雇用義務を果たしているのが現状です(厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告」2023年)。
また努力義務である70歳までの就業機会の確保を実施している企業は29.7%にとどまっています。