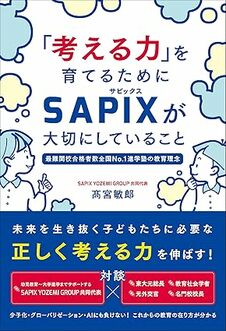ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
データで読み解く「日本経済」のリアル【エンタメ・スポーツ・事件編】
宅森昭吉(著)+ゴールドオンライン(編集)
データで読み解く「日本経済」のリアル【季節&気象・マインド・おもしろジンクス編】
宅森昭吉(著)+ゴールドオンライン(編集)
富裕層の資産承継と相続税 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】
八ツ尾順一(著)+ゴールドオンライン(編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
「失敗しない人材」に優しくすることが日本を緩やかな破滅に導く
濱田
課題解決的な学習に取り組み、「考える力」や「自分の知識を問い直す力」が伸びてくるのであれば、それはとても良いことです。しかし、企業や社会への目先の適応能力だけが高くなってもほとんど意味はありません。何より大事なのは、学生が長い人生の中で能力を発揮し、成長し続けられるような力を身につけることです。
課題解決的な学習といっても、大学としての対応には限界があります。昨今の大学は学生をかなり丁寧に育てるようになっていますが、その学生を受け入れる企業や社会の側でも、同じように丁寧に教育を進めてくれれば、なおよいと考えています。
例えば、以前の企業には「多少損失を出したとしても、また次に頑張ればよい」と、前に進むことを貴ぶ風潮があったと理解していますが、今の時代には、そのようなおおらかさが衰えてきたように感じます。
厳しい言い方かもしれませんが、成功を目指すのではなく、失敗をしないような人材に優しくなっているような印象を受けます。このような風潮を変えない限り、日本の社会も企業も大学も、長期的に伸びていく余地はないと私は思っています。
髙宮
東大教授で宇宙工学がご専門の中須賀真一先生は、「失敗が大事だ」と主張されています。宇宙開発のプロジェクトには非常に大きな資金がかけられています。300億円もかかるプロジェクトで失敗するわけにはいきません。そうすると、いかに小さい実験段階で失敗の経験が積めるか。そこが大事になってくるというわけです。
小さな失敗の経験を重ねるために、中須賀先生の研究室は、小さなロケットを打ち上げて、目的の地点に戻ってくるというコンテストに参加しているそうです。失敗してもさほど大きな損失になりませんので、安心して失敗を重ねることができるわけです。日本の教育には、そんな「失敗」が圧倒的に足りない。そのお考えにはとても感じるところがありました。
濱田
学生にハードな経験をしてもらうという意味では、東大でも、多くの体験活動のプログラムを設けたり、国際社会における指導的人材の育成を目的とする「グローバル・リーダーシップ・プログラム」を導入したり、といったことに積極的に取り組みました。このような多様な経験を通して、「自分を問い直す力」=「考える力」をどんどん伸ばしてもらう。自分が物事を眺める角度、自分の価値観だけで見てしまうと、どうしても物事の捉え方が狭く、固くなってしまいます。
異なる視点や価値観に触れることによって、「今の自分の在り方は違うのではないか」と問い直すことができる。しかもそれを授業の内外で学び、実践していく。それが成長につながると考えています。