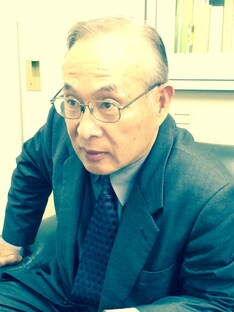継続すれば威力を発揮する基礎控除110万円の活用
ここまで、不動産の評価、分割による対策を説明してきました。ただ相続税対策には、それ以外にも王道と言われる対策があります。それは贈与です。しかし、実際には安易な形での贈与もかなり多いようです。したがって後日の税務調査で、その少なからぬものが否認の憂き目にあっています。何せ実施済みの贈与の否認は税務署員の得意技なのです。
ではまず、一般的な現金の贈与から見ていきましょう。
贈与は相続税対策の基本ですが、贈与税の累進性はかなり高くなっています。したがって、無税である基礎控除の110万円の効率的利用を中心として、贈与者の年齢や予想相続税額、さらには贈与税の特質をよく検討した上で、最適の贈与計画を考えていきたいものです。
まず、相続開始まで10〜20年の期間が考えられるのであれば、これと思う身内に毎年110万円の贈与を行うべきでしょう。たとえば、5人の親族に対して毎年110万円の贈与を10年続ければ、総額は5500万円になります。期間と人数を少し拡大して、多少の贈与税を覚悟すれば、1億円以上の贈与も十分可能となります。まさに「継続は力なり」です。
時間がないなら、税率を見極めながら金額をアップ
相続開始までの期間があまりないのであれば、予想相続税の税率(限界税率)をにらみながら、贈与額をアップしていきましょう。
贈与税は、贈与額に応じてもらった人に課税されます。この場合の贈与とは、民法上の贈与を言います。そして、そこには必ず「あげるよ」「うん、もらったよ」という両者の合意が必要とされています。ですから、親が贈与のつもりで子どもの名義で預金をしても、子どもがそれを知らない限り民法上も税法上も贈与は成立しないわけです(つまり、その預金は親の財産のままです)。
ところで贈与はその事実の把握に困難が伴います。そもそも贈与であるのかないのか、外見上は贈与の体裁をとってはいないが実態は違うのではないか、といった課税実務上の判定がかなり難しいのです。
そこで税務署はまず外観を重視して課税を行います。たとえば、対価の授受がないまま不動産や株式等の名義が変更されていた場合には、原則として贈与があったものとして取り扱います。
また、客観的に返せるはずはないと思われる額のものを「貸付金」と称して渡すようなケースも贈与と判断されます。たとえば「親が30歳のサラリーマンの息子の住宅取得に関して、5000万円を貸した」といったケースです。若いサラリーマンの年収では、5000万円など返せるはずがないからです。このような「ある時払いの催促なし」は、贈与とみなして課税するのです。
ただし、中にはそうではないケースもありましょう。その場合は納税者が税務署に対して、「これこれの事情や理由により、これは贈与ではない」旨の説明をきっちり行い、税務署を納得させれば課税はなしになります。
贈与に当たっては、これを実施したという証拠を残しておかないと、税務署に否認される恐れがあります。それには親の口座から子どもの預金通帳に、直接振り込むのが一番です。それにはその前提として、外見上も贈与の形をしっかり整えておくことが必要となります。
具体的に言うと、次のようなケースは否認される可能性が高いでしょう。
①子どもの通帳の契約印鑑が、親も使用している共通の印鑑である場合
②子どもの通帳の新規作成書類の筆跡が親のものである場合
③親の所有する株式等の配当金が子どもの通帳に振り込まれている場合
④子どもがその通帳の存在を知らなかった場合
⑤子どもの通帳を常に親が保管していることが明らかになった場合
これらはいずれも実質的に贈与されていないと判断される根拠になります。逆にこれらに
当てはまらない状況で、親の通帳から子どもの通帳に振り込んでおけば、特殊事情がない限り否認の恐れはまったくありません(この際、親の通帳に「○○へ贈与」とボールペンでメモしておくことをお勧めします。これも立派な贈与の証拠になります)。