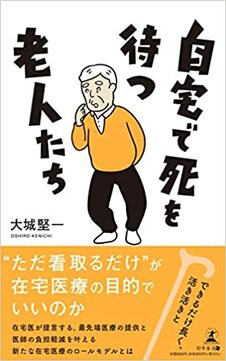医師同士や多職種との連携の難しさ
在宅医療における関係機関との連携の難しさは大きな課題です。
在宅医療では病院から退院時に在宅に移行する、あるいは在宅で療養していて急変したときに入院病床を確保するなど、地域の医療機関との連携が欠かせません。
また在宅患者に24時間対応をするには複数の医師が連携する必要がありますし、診療について専門の異なる医師にアドバイスを求めることもあります。こうした医師同士の連携も非常に重要です。
さらに高齢者の大半は、要介護認定を受けている介護保険サービスの利用者でもあります。在宅での生活を支援する訪問看護師や介護士、ケアマネジャーといった看護・介護分野の専門職との連携も不可欠です。
こうしたさまざまな関係機関・関係者との連携がなければ、生活の場で高齢者を支える切れ目のない支援は実現しません。地域の関係機関が手を組んでチーム一体となって高齢者を支えるのが、地域包括ケアシステムの基本的な考え方です。
しかし現実には、こうした地域の連携・ネットワークが必ずしもうまく機能しているわけではありません。
行政も地域包括ケアシステムや在宅医療に関するセミナーを開催するなどして、地域の関係者が連携するための下地づくりをしています。しかしながら実体は、それぞれの在宅医療クリニックが個別に動いて病院や介護保険事業所と関係づくりをしているため、連携先や連携体制は、クリニックによって量的・質的に差が生じています。
《最新のDX動向・人気記事・セミナー情報をお届け!》
≫≫≫DXナビ メルマガ登録はこちら