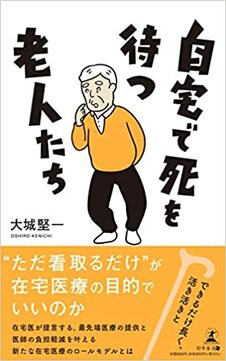在宅看取りばかりを重視する風潮
わが国の在宅医療が抱える課題の4つ目は、「看取り」の問題です。在宅医療についての昨今の風潮で私が気になっているのは、在宅医療の目的が「在宅での看取り」、つまり「家で死ぬこと」のようになっている点です。
書店へ行けば、在宅医療に関する書籍も多く並んでいますが、在宅死や平穏死、穏やかな最期など、在宅医療のなかでも終末期や看取りをテーマにしたものが圧倒的に多くなっています。
厚生労働省のデータから、全国の在宅医療クリニックの在宅看取り数をランキングし、「看取りの多いクリニック=良い在宅医」として紹介しているような雑誌もあります。また在宅医療クリニックのホームページ等でも、「家で最期を迎える」ことを強調しているところも少なからずあります。
最期をどこで過ごすのかは、確かに大切な問題です。日本は1950年代頃までは自宅で亡くなる人が8割以上を占めていました。その後、各地の病院や国民皆保険制度が整備され、1975年頃には病院で亡くなる人が逆転し、以降はずっと病院死が7~8割を占める状態が続いています。
近年、在宅死が注目されるようになった理由の一つに、病院で亡くなることの負の側面が知られるようになったことがあります。これまで病院では高齢になって命の終わりを迎える人に対しても、延命治療を施すケースが少なくありませんでした。
最近は少しずつ高齢者の終末期医療は見直されてきていますが、最期のときまで病院のベッドで治療を受けながら、また場合によっては家族が立ち会えぬままに人生を終えるのは確かにつらいことです。そのような病院での死に対し、在宅死がより自然で穏やかな死に方としてクローズアップされるようになりました。
また国民医療費抑制のために病院が病床削減を進めるなかで、多くの高齢者が亡くなる多死社会を迎えます。そこで国民の「死に場所」を確保するために、国は在宅で看取りを行う医療機関に診療報酬の加算をするなどして、在宅看取りの後押しをしています。
ですから今後、在宅看取りをする人が徐々に増えていくのは確実です。私のクリニックでも高齢者本人と家族が望むときには、在宅で看取りを行えるように支援しています。
しかし私自身は在宅医療に携わる医師として、在宅看取りばかりを重視する傾向には違和感を覚えます。
《最新のDX動向・人気記事・セミナー情報をお届け!》
≫≫≫DXナビ メルマガ登録はこちら