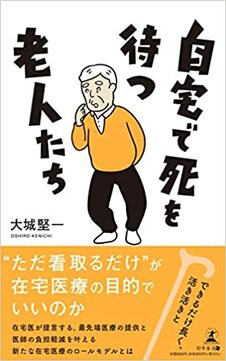医師同士の連携も、なかなかうまくいかない
病院との連携や地域の在宅医同士の連携は、決して簡単ではありません。
地域の複数の在宅医が連携して夜間・休日に診療することで、小規模クリニックの24時間対応を整備するというのも、現実にはそれもなかなかうまくいきません。
理由は、一口に在宅医療クリニックといっても実状はかなり異なっているからです。
外来診療と在宅医療の割合もクリニックによってすべて違います。1人の医師が10〜20人の在宅患者を診ているところと、医師数人で1000人を診ているところでは、医師の働き方も夜間の出動回数も異なります。
地域全体の24時間対応のために単純に在宅医の数で輪番制にしてしまうと、医師の負担の違いが大きくなり不満が出てしまいます。在宅医療には統一的なガイドラインはありません。クリニックや個々の在宅医により、診療方針や在宅医療についての姿勢・考え方もそれぞれ違います。
患者や家族から夜間に電話がかかってきたときでも、「とにかく患者宅に行く」という医師もいれば、「日常の管理や患者教育をしっかりしていれば、夜間の電話もすべて訪問する必要はない。状態によっては電話の指示でよい」と考える医師もいます。
そういう在宅医療の文化の違いにより、同じ地域の在宅医のなかでも「あの先生のやり方は納得できない」といった摩擦が起こることもあります。
各クリニックの在宅医はそれぞれ自分のやり方を最良と信じ、日々の診療に心血を注いでいます。地域医療のために貢献したいという思いは同じでも、時に状態が急変することもある高齢者の診療で、医師同士の意見の相違があったとき、どうすり合わせていくかは難しい問題です。
《最新のDX動向・人気記事・セミナー情報をお届け!》
≫≫≫DXナビ メルマガ登録はこちら