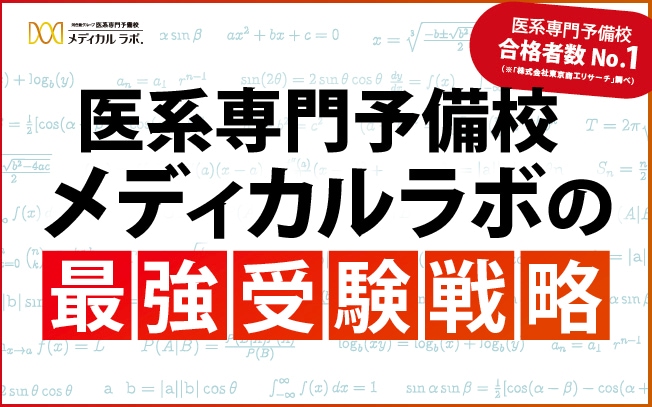児童手当の所得制限に関する2つの問題点
児童手当の所得制限に関しては、従来から以下の2つの問題点が指摘されてきています。
【児童手当の所得制限の問題点】
1. 所得制限自体が児童手当の制度趣旨に反している
2. 「世帯主」の所得を基準とするのは不公平・不合理である
以下、それぞれについて解説します。
◆所得制限自体が児童手当の制度趣旨に反している
まず、所得制限自体が児童手当の制度趣旨に反しているという批判があります。
児童手当の趣旨である「子育て支援」の要請は、所得の大小に関係なくすべての世帯に等しくあてはまるものであり、所得制限にはなじまないということです。
厳に、「貧困家庭」に特化した制度として、児童手当とは別に、学用品等の購入費用に関する「就学援助」等の制度があります。
それを考慮すると、所得制限を超えた世帯を「子育て支援」の対象から除外するのはかえって不公平になりかねません。
他方で、所得制限を設けない場合の「弊害」を見出すことは困難です。
「所得の再分配」や「格差解消」「救貧」の問題は、本来、社会保障制度や税制によって解決すべき問題です。児童手当という「子育て支援」の制度の枠内で考慮する必然性が乏しいといえます。
◆「世帯主」の所得を基準とするのは不公平・不合理である
しかも、「世帯主」の所得金額を基準としていることについても、不公平・不合理であるとの批判があります。
子育ては世帯単位で行われています。現在、子育て世代で圧倒的に多いのは「共働きの夫婦と子ども」の世帯です。それなのに、「世帯主」の所得を基準にすることの是非が問われています。
どういうことか。「世帯主と配偶者、小学生の子2人」の世帯で、以下の2つの異なるケースを比較してみましょう。
【「世帯主と配偶者、小学生の子2人」の世帯の2つのケース】
・ケース1:世帯主の年収が1,200万円、配偶者(扶養)の年収が103万円の世帯(世帯年収1,303万円)
・ケース2:世帯主と配偶者の年収が900万円ずつの世帯(世帯年収1,800万円)
まず、ケース1は、【図表2】の「所得制限限度額736万円・収入額の目安960万円」が適用されます。所得制限を超えてしまっており、児童手当は受け取れません。また、月5,000円の「特例給付」も対象外です。
次に、ケース2は、【図表2】の「所得制限限度額698万円・収入額の目安917.8万円」が適用されます。世帯主の年収が900万円なので所得制限内であり、児童手当を2名分(月額合計2万円)受け取ることができます。
ケース2の世帯の方がケース1の世帯よりも世帯年収が高いにもかかわらず、ケース1では児童手当を1円も受け取れず、ケース2では2万円を受け取れるということです。
これは不公平といわざるを得ません。
このように、現行の児童手当の所得制限は、児童手当のそもそもの制度趣旨に反するものであり、しかも、「世帯ごと」ではなく「世帯主」の所得を基準とする合理性が乏しく、不公平・不合理な制度と断ぜざるを得ません。
ついに与党幹部からも撤廃論が噴出…
児童手当の所得制限に対しては、与党幹部からも撤廃論が出ています。1月25日の衆議院本会議において、自民党の茂木敏充幹事長が、「撤廃すべき」という明言する場面がみられました。
岸田首相が提起した「異次元の少子化対策」の内容はこれから具体化されていくとみられますが、制度的欠陥が明らかな児童手当の所得制限の撤廃は、すみやかに手を付けるべき課題であるといえます。
\3月20日(金)-22日(日)限定配信/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処法
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【2/25開催】
相続や離婚であなたの財産はどうなる?
預貯金、生命保険、株…各種財産の取り扱いと対応策
【2/26開催】
いま「米国プライベートクレジット」市場で何が起きている?
個人投資家が理解すべき“プライベートクレジット投資”の本質
【2/28-3/1開催】
弁護士の視点で解説する
不動産オーナーのための生成AI入門
~「トラブル相談を整理する道具」としての上手な使い方~