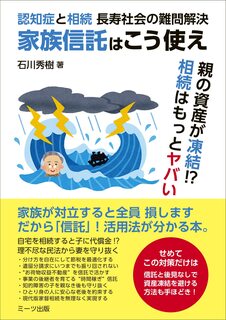知らないで済ませるわけにはいかない「成年後見制度」
「成年後見制度」は、財産管理や契約行為ができなくなった人のための救済制度であり、相続とは無関係です。しかし救済の過程で、遺産分割などに強い影響力を与えるので、知らないで済ませるわけにはいきません。
この制度最大のメリットは、主に以下3つが挙げられます。
▼凍結された資産を動かせる唯一の制度であること。
▼公的制度なので国の支援があり、認知症なのに独り暮らしで身寄りがない、収入が乏しく高齢、頼る人もなく老々介護の日々など、社会的に弱い立場にいる人を救済できること。
▼家族内の対立があり、親の財産を子が管理するには著しいリスクがありそうなときの代替手段になり得ること。
一方、「使いにくい」という批判もありますが、老後の暮らしを守る不可欠な制度です。
「認知症になってしまった」からの救済ツール
成年後見制度は、認知症対策の切り札のようにいわれています。
切り札とはいえ、家族信託とは存在する理由も違うし、立ち位置も異なります。ひとことで言えば、すでに手遅れになってしまった人のために使う“救済ツール”。何からの救済かといえば、第3部の民法の問題に関して書くことになる「認知症になるとできなくなること」からの救済です。このツールがなければ、本人も家族も、すでに困った状態に陥っているわけですから、救い出すことができません。
家族にとっては、もちろん使わずにすむよう対処しておきたかったところでしょう。気持ちの面からも、費用の面からも代償が大きいですからね。
成年後見制度の用語
成年後見制度は、民法の枠内にあり、その基本的な観念は委任と代理です。
しかしこの制度の委任者は、事理弁識能力を喪失しているか欠けている人を想定しています。そうすると委任の意思が不完全なので、本人や本人の親族など特定の人が申立人となり、①財産管理と②介護認定など医療や福祉関係の手続き(これを「身上保護」といいます)をする代理人を選任するよう家庭裁判所に審判開始を申立てます。申立てを受け家庭裁判所は後見人等を職権で選任します。成年後見人等は以後、本人の公的代理人として上記2つの職務を遂行する義務を負います。
このような法定後見には、判断能力の低い順に成年後見・保佐・補助の3類型があります。親族も後見人等の候補になれますが、最近は士業などの専門職後見人の比率が8割くらいを占めています。
法定後見とは別に、任意後見契約も制度の一翼を担っています。任意後見人は依頼者が自由に指定できますが、任意後見は家庭裁判所が任意後見監督人を選任して開始となるので、一定の制約は受けます。