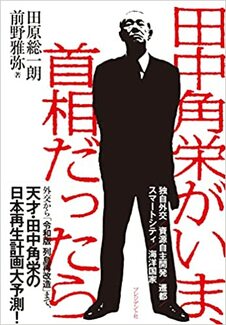お金で人の心までは買うことはできない
■若手官僚に早くから目をつけて交流した
『日本列島改造論』は官僚が全面協力して生まれました。実はこのときに動いた官僚の中には、角栄が若い頃から目をかけていた連中が多かった。角栄は1947年4月、28歳で当選、政治家として立ち、1957年には39歳の若さで郵政相となったが、国の政策や法律については20歳代から勉強を始めていた。
角栄は早くから霞が関の官僚の優秀さに着目し、20〜30歳の若手官僚と交流を重ねながら、丁々発止、議論する機会を設けてきたのだった。
高等小学校卒の角栄だったから、大半が東大出のエリート官僚たちと、もともとのつながりは何ひとつない。人を頼りそれぞれの省庁で「将来、見込みがある」若手官僚を集めてもらい、その若手官僚たちと徹底的に議論することで、関係を積み上げていったのだった。六法全書の大半を暗記していたという角栄である。次第に官僚たちも「この男なら将来一緒に仕事ができる」と感じたに違いない。
そんな若手官僚たちが、角栄のもくろみどおり、時間を経てそれぞれの省庁で出世の階段を昇った。そして角栄を支える立場となったのだ。『日本列島改造論』では、まさにそうした縁が生きた。「コンピューター付きブルドーザー」と言われた角栄の「コンピューター」の部分として働いてくれたのだった。
一橋大学名誉教授で元大蔵官僚の野口悠紀雄は、「角栄が人心を掌握できたのは『金力』だと言われるが、決してそうではない」と証言する。
確かに角栄と金は切っても切れない。石原慎太郎が『文藝春秋』に発表したところによると、「ある大蔵省の高官が私に話したことだが、田中角栄氏が大蔵大臣に就任するまで、大蔵大臣から大蔵官僚に対する中元や歳暮はせいぜい官僚夫人用のゆかた地かハムの詰め合わせ程度だった」
「それが彼(角栄)が大臣に就任して一挙に、当時の金で数十万円の現金となった」
角栄はお金の力をよくわきまえていた。ここぞという勝負時に角栄はお金を使った。それは事実だ。
しかし、同時にお金の怖さも知っていた。お金で人の心までは〝買う〞ことはできない。それをわかっていた。秘書の早坂茂三が現金の配達人として全国を飛び回るように命じられたとき、角栄はこう言ったのだという。
「この金は心して渡せ。『ほら、くれてやる、ポン』、なんて気持ちが、お前に露かけらほどもあれば、相手もすぐわかる。それでは100万円の金を渡しても、1銭の値打ちも
ない。届けるお前が土下座しろ」
お金の切り方は難しい。相手のプライドを傷つける場合もある。角栄は自分がお金で苦労しただけに、お金の負の側面も限界もまたよくわかっていた。
だから官僚とのつきあいも、最後のところは仕事だった。当時も今も官僚には国士が多い。角栄の秘書官だった小長にしても、「日本がなぜ第二次世界大戦に追い込まれていったのか、あの失敗を繰り返さず日本が発展していくにはどうすべきなのか、について大学で徹底的に研究した。
そこで得た結論が貿易立国。これで国を立てていくしかないと確信し、通産省に入省した」という。国のために仕事をしたいのだ。角栄はここを理解していた。