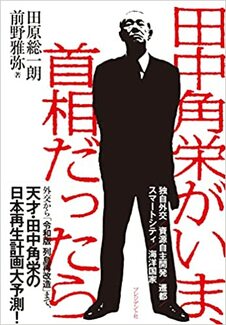「俺がやる。総理に電話をつなげ」
■日米繊維交渉にみる田中角栄の「仕事力」
1971年7月。田中角栄は通産大臣に就任した。大臣に就任してまず直面したのが日米繊維交渉。当時、日本からの繊維製品が米国市場を席巻、貿易摩擦が大きな問題となっていた。もはや放置しておくことはできない。事態は深刻だった。対処を誤れば沖縄の返還問題にも影響を及ぼしかねない高度かつ複雑な交渉だった。その収め役に選ばれたのが角栄だった。
このとき、通産大臣になるということはそういうことだった。角栄はそれまでの大平正芳や宮沢喜一といった官僚出身の歴代通産大臣では思いつかないウルトラCを繰り出すことで、難関を突破した。
そのウルトラCとはこうだ。まずは繊維業界にアメリカ向けの繊維製品の輸出規制を呑ませる。これでアメリカは黙り、貿易摩擦は収まる。次に繊維業界。繊維業界には輸出規制の代償問題が発生するが、単にお金だけを渡せばいいというものでもない。
名門意識の強い繊維マンたちのプライドが傷つく。黙ってはいない。そこで政府が古い織機を買い上げるかたちをとる。生産性の低い旧式の織機を政府が買い上げる形をとり、そのお金で繊維業界は設備更新を進めるのだ。これなら繊維業界の顔も立つし、産業政策上も問題はない。
「よし、これで行こう」
通産官僚と膝詰めで議論し、旧式織機の買い上げ案で方向性が決まったが、1つだけ問題が残った。それは資金だ。旧式織機の買い上げ資金はざっと2000億円。2000億円といえば、当時の通産省の一般会計予算の半分である。そんな巨額の資金をどう捻出するのか。それが問題だった。うんうん唸る官僚。しかし、そんな官僚たちを尻目に角栄はこう言った。
「俺がやる。総理に電話をつなげ」
当時の総理大臣は佐藤栄作である。実際に佐藤に電話をつなぐと、角栄は官僚たちの目の前でさっと状況を説明し、言葉どおりに資金手当ての約束をとりつけてしまった。
そして、ここからが角栄の縁が生きた。秘書官の小長に「俺の名刺を持ってきてくれ」と頼み、それを受け取ると、さらさらっと万年筆でこう書いたのだった。
「徳田博美主計官殿 2000億円よろしく頼む」
そして小長に「これを大蔵省に届けろ」と言ったのだった。
大蔵省主計官と言えば実質、予算配分の決定権を握る。権力は絶大だ。ただ、主計官は何人かいる。担当を決めてそれぞれの領域で仕事をしているのだ。大蔵大臣だった角栄はそれを知っていて、通産省関連の担当がどの主計官なのかをフルネームで正確に記憶していた。
名刺を渡さなくても、総理に電話しているのだから話は通ったはずだ。大蔵大臣の水田三喜男にも総理大臣への電話の後、直接「総理も了承している。2000億円出してくれ」と掛け合い、話をつけている。問題はない。それでも現場が少しでも円滑に仕事を進められるよう、自分の縁を使ったのだった。
■「記憶力よりも、胆力」
とにかく角栄は人の名前をよく覚えた。出身大学、官僚なら入省年次、家族構成まですべてだ。
経済学者で一橋大学名誉教授の野口悠紀雄は、1964年4月、大蔵省に入省した。このときの大蔵大臣が角栄だった。入省が決まり、まず大臣と面通しとなり大臣室で整列して待っていると、角栄が勢いよくドアを開け入ってきた。そして「おっ」と言うと、いきなり、角栄の一番近くにいた野口の同期の手を握り、こう言ったのだという。
「やあ、秋山君、ようこそ大蔵省へ。頑張ってくれたまえ」
確かに角栄が手を握った青年の名前は秋山だった。そして、それは秋山青年だけでは終わらなかった。2番目の青年の名前も角栄は呼び、3番目の青年の名前も呼んだ。そしてとうとう20人全員の名前を一人も間違うことなく呼び、握手してしまったのだった。
「これには驚いた」と野口は言う。
大蔵省の入省試験に合格した野口たちだ。20人くらいの名前なら覚えることができたはずだが、それでも100%確実ではない。万が一間違えれば、その瞬間に信頼は地に落ちる。「絶対に間違えない」という自信がなければできないことだった。角栄はそれを堂々とやってのけた。
「記憶力というよりは、その胆力に圧倒された」