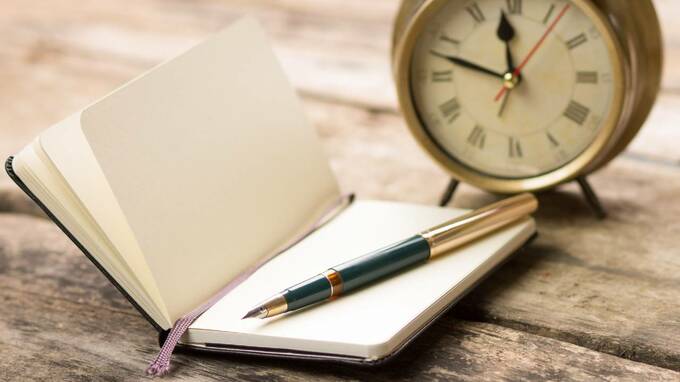「自筆証書遺言書保管制度」にどんなメリットがある?
【相談内容】
将来の相続に向けて遺言書の作成を考えており、自分でいろいろと調べています。
そのなかで、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになったことを知りましたが、どのようなメリットがあるのでしょうか。
【回 答】
自筆証書遺言を法務局に保管することにより、紛失や偽変造の恐れがなくなるというのが、いちばん大きなメリットだといえます。
法務局では遺言書の原本に加え、遺言書をデータ化した記録が保管されることになります。遺言書の原本は、物理的に1ヵ所の法務局でしか閲覧できませんが、画像データにすることで、どこの法務局でも閲覧が可能になります。
また、遺言書保管制度では、保管前に法務局で形式上のチェックが行われるため、相続発生後の検認が不要になります。このため登記も含め、スムーズな相続が可能になるといえるでしょう。
管轄する法務局は、遺言者の住所地の法務局となります。遺言者の住所地が横浜市であれば、横浜地方法務局で保管を受けることになります。
遺産分割前の「預金の払い戻し制度」とは?
【相談内容】
父親が亡くなりました。ところが、父親の銀行口座が凍結されてしまい、葬儀費用や病院への支払いなどに必要なお金が工面できません。
知人から、遺産分割前の「預金の払い戻し制度」の利用を勧められたのですが、どのようなものなのでしょうか。
【回 答】
相続が発生した際、遺産分割の対象となる被相続人名義の口座は、遺産分割が終わるまで、相続人単独では、原則として預貯金の払い戻しが受けられませんでした。そのため、葬儀費用や生活費の工面ができないといった問題がありました。
しかし、法改正により、請求できる金額に上限はあるものの、相続人単独で、遺産分割を待たずに預貯金の払戻しを請求できる、遺産分割前の預貯金払戻し制度が制定されたのです。これは平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」の一部で、令和元年7月1日に施行されました。
●払い戻しができる額の上限は?
下記の計算式に基づいて算出されます。
相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、金融機関ごとに150万円までと定められています。複数の銀行口座に多額の残高がある場合の例ですが、A銀行で150万円、B銀行で150万円…と、それぞれの銀行に対して請求することも可能です。
●払い戻されたあとの遺産分割における取り扱いは?
払戻金は、払い戻しを受けた相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされます。ほかの相続人との公平を図るためです。
ただし、これらはある意味「その場しのぎ的な手段」ともいえます。実際の手続きは、多くの書類をそろえる必要がある(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本あるいは全部事項証明書、相続人全員の戸籍謄本あるいは全部事項証明書、払い戻す人の本人確認書類・印鑑証明書・実印)など、かなり煩瑣であり、また、相続放棄ができなくなるなど、慎重に検討すべき問題もあります。
円満な相続手続きのためにも、遺産分割協議書の作成をお勧めします。
近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】