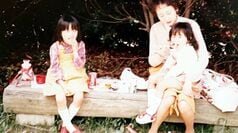「予期せぬ債務」の場合相続放棄できることも
法定相続人が、被相続人が亡くなり、自分が相続人であることを相続発生日に認識していた場合、相続発生から3ヵ月経過後に相続放棄をすることはできるのでしょうか?
3ヵ月経過後の相続放棄について、昭和59年4月27日の最高裁判例では、3ヵ月以内に相続放棄をしないのが、「相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人との関係などから全く存在しないと信じるのが相当な場合において、被相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識すべき時から3ヵ月を起算すべき」としています。
しかしながら、実務上は、法定相続人が、被相続人の財産の一部を認識していたとしても、予期せぬ債務があとから発覚したなどの場合には、家庭裁判所は相続放棄を受理する傾向にあります。
これらの判断には法的な知識が必要であるため、3ヵ月経過後の相続放棄については、可能な限り早く弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
相続放棄の「申述受理」と「有効性」
ここで、相続放棄の申述受理と相続放棄の有効性についても少し補足いたします。
相続放棄の申述受理とは、相続人の相続放棄をする意思表示を家庭裁判所が公証するもので、相続放棄の要件を明らかに欠くとはいえない場合は、申述が受理されます。
大半のケースでは、相続放棄の申述が受理されればそれで足りることが多いですが、申述の受理=相続放棄が有効というわけではないため、相続放棄の申述が受理されたあとでも被相続人の債権者は、相続人に対し、債権の取り立ての訴訟を提起することができます。
訴訟を提起された場合に、相続放棄の申述受理証明書を示し、相続放棄の事実を主張することで、はじめて裁判所が、相続放棄の要件をみたしているか、実質的に審理をして、相続放棄の有効性について判断します。
相続発生から3ヵ月を経過した相続放棄については、被相続人の債務が3ヵ月経過後に発見された、債権者から教えられた債務金額に誤りがあったなどの事情がある場合、家庭裁判所は申述を受理する傾向があります。
しかしながら、相続放棄が受理されても、債権者から訴訟を提起され、相続放棄の有効性が争われることもありますので、3ヵ月経過後の相続放棄については、専門家に相談のうえ、対応をするようにしましょう。
3ヵ月を経過しているからといって、ご自身の判断で相続放棄を諦めるのではなく、必ず専門家に相談のうえ、相続放棄の可否について検討するようにしましょう。
注目のセミナー情報
【国内不動産】4月26日(土)開催
【反響多数!第2回】確定申告後こそ見直し時!
リアルなシミュレーションが明かす、わずか5年で1,200万円のキャッシュを残す
「短期」減価償却不動産の節税戦略
【資産運用】5月10日(土)開催
金価格が上昇を続ける今がチャンス!
「地金型コイン」で始める至極のゴールド投資