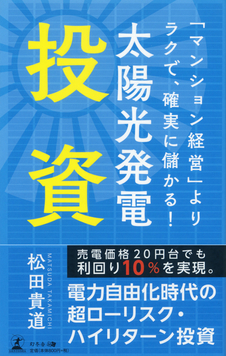変化している太陽光発電事業者のコスト意識
時代に即した取り組みポイントを見ていく前提としてまず、いまの時代とは太陽光発電投資にとってどのような時代なのかをざっと確認しておきましょう。
太陽光発電投資は発電した電気を売って儲けます。いまは太陽光のような再生可能エネルギーの発電コストを下げて、その普及を図るのが狙いですから、政策誘導的な売電価格を想定しています。その価格が下がっているのは、これまで見てきた通りです。
これはひとえに、発電コスト、つまり太陽光発電システムを設置する費用が下がってきているからです。設置費用が下がっているなら、それに見合った価格での買い取りでも太陽光発電に取り組む投資家や事業者のモチベーションを下げることはない、との判断でしょう。これによって、メガソーラーと呼ばれる出力1MW(=1000kW)以上の規模を持つ太陽光発電所が、事業採算性を厳しく見込むようになったと言われています。
ある事業者は、太陽光発電パネルは国内メーカーのものを優先して導入してきたものの、今後は、国内外のメーカーを問わず、条件の良いもの、つまりより安価なものを導入する方向に調達の考え方を見直す、と伝えられています。
またある事業者は、メンテナンス費用の削減を図ろうと工夫を凝らしています。太陽光発電パネルの不具合検査にドローン(無人航空機)を活用し、コストを抑えながら発電量の低下を最小限にとどめる方針をとる、と伝えられています。
これらの動きは、個別発電所の採算性は厳しく問うものの、決して太陽光発電事業そのものからの撤退を考えているわけではありません。やはり将来のエネルギー動向をにらんでいるのです。
太陽光による発電はまだまだ必要とされているという見方です。その見方の確かさは、経済産業省「長期エネルギー需給見通し」でも裏付けられています。しかし一方で、太陽光で発電した電気の受け入れ体制が十分ではないという点が問題視されています。太陽光発電システムを設置しても、発電した電気をその近くの系統ですぐに受け入れられるとは限らないというのです。
場合によっては新しく設備を整える必要が生じることから、太陽光発電投資を始めようとする投資家にとっては費用負担がかさみ、好ましくありません。ところが、こうした受け入れ体制の問題は時間の経過とともに解消されるのではないかとの見通しが、専門家からは聞かれます。
発電した電気の受け入れ態勢が万全になる3つの理由
理由の一つは、原子力発電所の廃炉によって送変電設備に空きが生じるという点です。原発の廃炉は、原子炉等規制法で発電用原子炉の運転期間が原則40年と定められたため、老朽化したものが対象になります。運転期間の延長に関して原子力規制委員会の認可を得ない限り、運転を継続することはできません。この規定によって廃炉の決まった原発はすでに5基あります。
したがって、その原発から電気を送っていた系統の送変電設備には空きが生じるはずなのです。もちろん、その空きを使えるようになるのは太陽光発電所に限りませんが、受け入れ体制に余裕が生まれるのは確かです。
エネルギーの地産地消やガスエンジンなどから熱と電気を生み出すコージェネレーションシステムの普及によって送電線を使用しなくなる、という理由も2番目に挙げられます。例えば自家発電であれば、送電線は不要になるわけです。
3番目の理由は、電力システム改革を背景とするものです。改革によって発電と送電と小売り、これら3つの事業が分離される中で、送電事業を担う会社が送電線の建設に乗り出す可能性が見込める、というのです。発電した電気の受け入れ体制は送電事業を担う会社によって整備されていくのではないか、という見通しです。
電力システム改革はいまの時代を語るうえで重要なキーワードなので、あらためて詳述します。つまり、電源構成の見通しに照らすとまだ伸びしろが見込めるうえに、送電線に空きが生じたり新規投資で整備されたりすることから、発電した電気の受け入れ体制は追いついてくる、という見方です。
こうした見方が成り立つからこそ、太陽光発電事業者は採算性には厳しい目を向けるようになりながらも、事業継続の構えを崩さないのです。発電した電気の受け入れ体制が改善していくと見られる理由は、まだあります。それは、電力会社間の電力融通が一段と進むことです。電力融通が進めば、需要に対して供給が余る地域から需要に対して供給が足りない地域に電力をもっと送り込むことができるようになります。
電気がためられないことから原則とされる「同時同量」を、一つの電力会社の管内だけでなく、もっと広い地域内で実現すればよくなるのです。東日本大震災のとき、複数の発電所が被災し稼働を停止したことから東北電力や東京電力の管内で計画停電を実施したことはご記憶かと思います。
このとき、需要に対して不足する電力を、隣接地域を所管する電力会社から引き入れればよいではないか、つまり、地域間で電力を融通し合えばよいではないか、との声が上がりました。しかし、設備の制約からそうした対応が十分にとれなかった経緯があります。設備というのは、電気の周波数を変換する設備です。
ご存じのように、東京電力管内が周波数50ヘルツであるの対し、隣接する中部電力管内は周波数60ヘルツです。異なる周波数のまま電力を融通したのでは生活や産業に支障が生じることは、すでにご説明した通りです。電力を融通するには、周波数の変換が不可欠なのです。その経緯を踏まえていま、東京電力と隣接する中部電力の間では、電力の融通強化に向けた設備の整備が進められています。
これは、長野県内にある東京電力の周波数変換所を、設備容量60万kWから同150万kWに増強するものです。東京電力と中部電力の間ではこの変換所を通じてより多くの電力を融通し合うことができるようになるのです。2020年度を目標にすえています。
国としても、経済産業省の傘下に電力広域的運営推進機関を立ち上げて、送電網をリアルタイムで監視し、全国レベルで電力を融通するシステムの構築や広域連系系統の整備などを行っています。こうした地域間の連系に弾みがつくことは、太陽光発電投資にとってプラスに働くはずです。