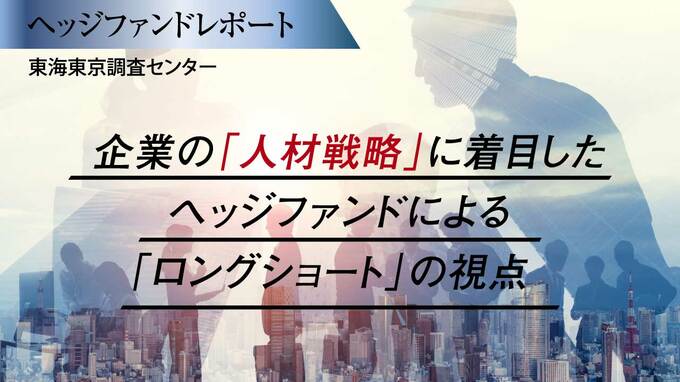「商社の資源事業」で見る経営戦略と人材戦略の矛盾
人材版伊藤レポートをもう少しわかりすく説明するなら、商社の資源ビジネスを取り上げると理解が進みやすいだろう。
化石燃料資産である石油、石炭、天然ガス等は、これまで商社の資源ビジネスとして収益の一つの柱を担ってきた。とはいえ、ESG投資が中長期的に拡大することが予想されるなか、再生可能エネルギーの浸透により、将来、石油、石炭、天然ガスビジネスは「座礁資産(市場環境や社会環境の変化により、価値が大きく毀損する資産)」と化す可能性が高まってきている。
短期的な収益だけを考えた場合、石油、石炭、天然ガスビジネスに経営的に力を入れたほうが、コストが割高な再生可能エネルギービジネスに取り組むよりも収益が上がりやすいといえよう(残存者メリットを享受)。とはいえ、中長期的にはこれらのビジネスは衰退していく可能性も高く、経営・事業部門が大きく傾くようなリスクを抱えることにもなる。
また人事上、過去から現在の目に見える功績だけを考えた場合、まだあまり実績のない中長期的ビジネスである再生可能エネルギーに関わる人材より、過去から現在まで実績を上げている石油、石炭、天然ガス事業を担っている人材を高く評価したほうが足元の社内評価では整合性がつきやすい。長年の経験も加味されるため、年功序列型システムにもマッチする。
とはいえ、このような足元の整合性に注力しすぎた人事制度・評価をとっていた場合、社員が合理的な行動をとるのであれば、中長期的に有望だと判断していても、あまり短期では評価されない再生可能エネルギービジネスをやりたいという人は少なくなる。
また優秀な社員を化石燃料ビジネスにとどまらせる誘因が社内で働くことで、将来有望な再生可能エネルギービジネスに経営・人的資源を集めることが難しくなり、将来的な企業の競争力が低下するリスクを抱えてしまう。加えて、このような中長期なトレンドと社内評価の矛盾を見極めた若手・中堅社員が現状の人事評価システムに不満・不安を抱き、社外に流出してしまうリスクも抱えることとなる。
このような総合的なリスクを回避するため、経営として短期は石油、石炭、天然ガスで収益を維持しながらも、中長期の視点で成長分野である再生可能エネルギービジネスにシフトするため、優秀な人材を部門やビジネスに関係なく、また属人的な評価ではなく、専門性に応じて客観的、合理的に評価するシステムを整える必要がある。
将来有望だが、今あまり利益が上がっていない部門において、他の稼ぎ頭の部門の人材と同様、専門性をベースにフェアに評価される形をとることができれば、経営・人的資源をバランスよく社内でシフトさせ、中長期的な企業価値の向上につなげられる可能性が高まる。まさに経営戦略と人材戦略が一体と捉えられる所以はここにあるといえよう。
足元の大手商社は、すでに新たな専門人材評価システムを導入し、経営面から積極的に座礁資産を切り離しにきている点は、中長期的な企業価値の向上を図る意味で評価できる動きと考えられる。
■まとめ
株式市場において、ESGの「S」の側面である人材戦略と経営戦略を一体化させ、日本企業が積極的に取り組むことが中長期の業績・企業価値向上につながる一つの切り口・道筋になるとの認識が強まれば、海外投資家(特に年金などESGを重視した中長期の投資家)を中心とした持続的な資金流入が期待でき、日本の株式市場の底上げにつながってくるとみられる。
そのため、中長期の「ESGロング戦略」をとっている投資家にとってはここに商機があるだろう。また、「ロングショート戦略」をとっているヘッジファンドにとっては、経営と人材戦略の一体化ができている企業をロング、できていない企業をショートする誘因が働きやすくなろう。
中村 貴司
東海東京調査センター
投資戦略部 シニアストラテジスト(オルタナティブ投資戦略担当)
\投資対象は株式、債券だけではない!/ 金融資産1億円以上の方向け
「本来あるべきオルタナティブ投資」 >>他、資産運用セミナー多数開催!
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【2/25開催】
相続や離婚であなたの財産はどうなる?
預貯金、生命保険、株…各種財産の取り扱いと対応策
【2/26開催】
いま「米国プライベートクレジット」市場で何が起きている?
個人投資家が理解すべき“プライベートクレジット投資”の本質
【2/28-3/1開催】
弁護士の視点で解説する
不動産オーナーのための生成AI入門
~「トラブル相談を整理する道具」としての上手な使い方~