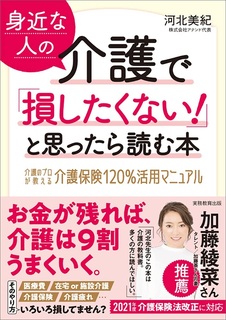「介護の経済的負担を楽に」活用できる様々な制度
親の介護という、いままでの日常になかった生活パターンが加わると、最初は気が張って、時間もどうにかやりくりできるものです。しかし、長期戦になるにつれ少しずつ「疲れ」が出始めます。しかもその疲れを自分でなかなか自覚しにくいのが、家族介護の怖いところでもあります。
介護を続けるためには、また自分の心と体を少しでも楽にするためには、どうしたら良いのでしょうか? 家族間の連携や介護のプロによるサポートに加え、もうひとつ大切なのが「経済的基盤」です。ここでは、お金の話をしたいと思います。
たとえばおむつ代ひとつとっても、ご家族にとってはいままでになかった痛い出費です。しかし、国や市区町村の制度を利用すれば、年間100万円も介護費用を抑えられることがあります。
生活するためにお金が欠かせないように、介護に関してもお金の有無で選択肢が変わります。利用できる制度をしっかり調べて、経済的負担を少しでも楽にしましょう。
国や市区町村の「手当て・支援制度」一覧
まずは地域包括支援センターへ相談することがおすすめです。要介護認定の申請をして、介護サービスの開始や、介護内容を充実させるための地域情報を集めてもらうためです。
一方、介護サービスとは別に、経済的な支援(手当)の制度を申請する場合は、地域包括支援センターではなく市区町村の役所内にある「介護保険課窓口」へ行く必要があります。
要介護認定と違い、手当の申請の多くは基本的に地域包括支援センターに代行してもらうことができません。国や市区町村には、具体的に次のような手当や支援制度があります(各市区町村によって支援の内容は異なります)。
<国や市区町村の手当て・支援制度>
●特別障害者手当
●電車やバスなどの割引き(東京都はシルバーパス)
●紙おむつの支給
●介護手当(総称。実施していない市区町村もある)
●介護保険負担限度額認定(介護保険施設の居住費●食費の軽減)
●理美容割引券
●詐欺等被害防止機器の貸し出し
●自動消火装置や電磁調理器具の給付
●認知症ホットライン(物忘れ、不安や困りごとなど)
●徘徊高齢者探索システム(GPS端末機)
●補聴器購入の助成
●福祉タクシー乗車券
●車いすの貸し出し
●配食サービス
●24時間緊急通報システム、月1回の安否確認
●民生委員や地域包括支援センターによる目配り訪問
●寝具乾燥消毒、福祉理美容サービス(券の交付)
●ボランティア訪問によるコミュニケーション(月1回)など
※上記は一部、地域包括支援センターでも申請可