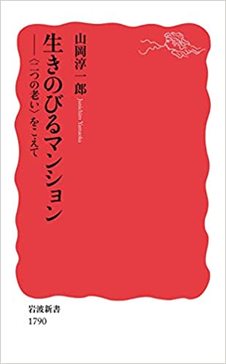「タワーマンション」が首都圏に増え続けるワケ
超高層マンションが続々と建てられています。タワーマンションは眺望とホテル並みの豪華な共用設備やサービスが売り物です。以前は富裕層しか手の届かない高嶺の花でしたが、棟数が増えるにつれて、より一般化してきました。
それとともに急激な人口集中によるインフラ整備の遅れや、新旧住民の分断現象も起きています。多くのタワーマンションが、管理組合運営に手こずり、修繕や設備更新のノウハウが確立されていません。
人気の高さとは裏腹に「不都合な真実」が顕在化してきました。課題を掘り下げるために、まずは超高層マンションが林立する背景を見ておきましょう。
超高層マンションに法的定義はありませんが、高さ60メートル、20階建て以上とされています。その第1号は、1976年に住友不動産が埼玉県与野市(現さいたま市)に建設した「与野ハウス」(21階建て)だといわれています。
初期のタワーマンションは、都市計画上の規制により、広大な敷地を要しました。そのために地価の安い郊外や、河川沿いに建設され、数も多くはありませんでした。
流れが変わったのは、1997年。バブル経済崩壊後の不良債権処理が不動産・建設業界にのしかかるころでした。国が「高層住居誘導地区」を導入し、東京湾岸エリアの工場や倉庫、貨物ヤードなどの跡地にタワーマンションが建てられます。

2000年代に入ると、「都市再生」「都心回帰」を合言葉に駅前地区の「市街地再開発」に拍車がかかりました。バブルのツケ払いが超高層建設に託され、首都圏から近畿圏、地方中核都市へと波及します。2008年9月のリーマン・ショックで供給量は減り、2011年の東日本大震災で落ち込みますが、2020年の東京五輪をメルクマールとして増加に転じました[図表1]。
不動産経済研究所のデータによれば、19年以降に完成予定の超高層マンションは、全国で300棟、11万4079戸。そのうち73.6パーセントを首都圏が占めています。東京23区内に52.5パーセントが集中しており、近畿圏が12.8パーセント、福岡県3.4パーセント。
景気に左右されながらも、東京都心部や湾岸エリアを中心に超高層マンションは大量に供給されています。最近は、内陸部の市街地にも建ち続けています。
なぜ、タワーマンションは増えるのでしょうか。


![[図表1]超高層マンション竣工・計画戸数](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/3/4/450/img_34b389fa2aa22634a291f2b82e65eb5d150525.jpg)