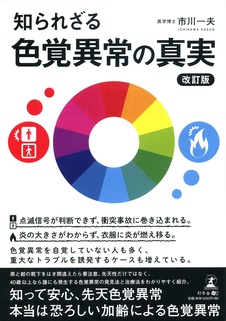色覚異常は「症状が軽い人」ほど危険
先天色覚異常は、確かに軽度であれば、日常で困るようなことは少ないでしょう。しかしそれゆえに、他人とちがうという違和感をなんとなく抱えていても、自らが色覚異常であると気づかないケースがあります。
しかし、色覚異常であることを認識していないというのは、実は極めてリスクの高い状態といえるのです。症状がかなり軽度で、昼間や明るい光の下など、対象を見る条件がいい時にはまったく色を間違えるようなことはなくとも、夜間であったり、形が小さかったり、複数の色が混在したりというような悪条件になると、間違う可能性は途端に跳ね上がります。
強度の色覚異常であれば、ほとんどの人は自分の色覚が他人と違うということを認識しています。彼らは人生を歩んでいく中で自分の苦手な色を知り、それに対し注意深く行動する習慣がついていますから、トラブルを避けることができます。
ところが症状が軽度であると、自分が赤に弱い、緑を見間違うということが意識できません。悪条件下でものの判断を迫られるような状況になってはじめて何かおかしいと感じます。それが服の間違いや絵の塗り間違いですめばいいのですが、信号機を見間違って事故を起こしてしまうことも十分に考えられます。その場合、自己責任として損害をこうむってしまうこともあるのです。
どんなに軽度であっても、自らが色覚異常であると認識すること。これが何より大切です。そのためには、やはり検査を受けなければいけません。眼科であればどの医療機関でも簡易検査を行うことができ、色覚異常かどうかが判断できますから、もし自分自身や家族で何か少しでも思い当たる節があれば、一度、検査を受けてみることをお勧めします。
「診断結果を変えてほしい」と頼む親もいるが…
色覚異常であることが明らかとなり、自らが苦手な色や状況を認識できれば、それをもとに多くの対策が打てます。
まず、苦手な色に対する意識が変わり、それらに関わる時には慎重になりますし、よりていねいに判断しようとするでしょう。結果的に、見逃しや見間違いが減り、仕事などの質を落とすことなく生活できるはずです。
また、信号灯や警告ランプなどに対し、以前よりもさらに注意深く捉えようとすることで、身に迫る危険をより素早く察知することができます。
1秒の判断が命運を分けるようなこともありますから、これは非常に大切なことです。わが子の色覚異常が強度と知った親の中には、どうしてもその現実が受け入れられず、子どもの将来を考えるあまり、診断を軽度に変えてほしいと医師に頼むような人がいます。また、軽度の診断が下りるまでさまざまな病院を渡り歩く人もいると聞きます。
それよりも親が考えるべきことは、子どもをどう導いてあげるかです。人生の早い時期から、親が「わが子は色の見え方が違う」とわかっていれば、それと共存していけるような生き方に、子どもを導くことができます。

「小学生になる前の色覚検査」が子どもの人生を守る
それでは検査は何歳で受ければいいのでしょうか。
私は個人差はあっても一般的に5歳くらいになれば、正常か異常かを見分けることができると考えています。
小学校に入学するくらいになれば、色覚検査表を使った検査はできるようになるはずです。特に強度の色覚異常である場合、小学校入学前から親がそれを把握していることが、重要になってきます。
たとえば、小学校で色の違いがわからないことで友達にばかにされたり、白い目で見られたりすることが起こるかもしれません。色覚異常であることを教師や本人も知らなければ、単純に間違いとして責められることもあるでしょう。こういった悲劇を描いた文献があるので、ここで紹介します。
*************
――以下引用
多くの色盲、色弱者がそうなのでは無いかと思うのだが、僕の場合は、小学校の図工の時間に、紅い薔薇(ばら)を御納戸(おなんど)色に、葉を茶色に描いた事で発見された。色覚異常に無知だった担任の教師は、見た物を見た儘(まま)に描かない子供は心の捻(ね)じけた子供です、と叱り、僕の画を級友に示した。級友はどっと嗤(わら)い、囃(はや)し、僕は教壇の上に佇(た)たされ、泣いた。
次の週も同じ事の繰り返しだった。宮島の大鳥居の模写だった。又僕は佇たされ、今度は声を上げて泣いた。何が何やら判らなかった。子供にとっては驚天動地だった。見た通りに、見えた通りに描き、塗ったに拘らず、教師は詰(な)じり、級友は囃し立てる。
図工の時間があった水曜日――今も覚えている――あの恐ろしい時間が待っていると思うと、脚が震るえ、僕は学校に行く事を怯え、毎水曜日にはお腹が痛い、咽喉(のど)が痛いと嘘を言って学校を休んだ。美を教える筈の時間は、小さかった僕に、生まれて初めての嘘を吐(つ)く事を教えたのである。悲しい記憶である。
然(しか)し、何時迄(いつまで)もそんな事は続かなかった。小学校二年生に変った時、色覚異常に対して知識と理解のある先生が担任となり、僕は救われた。鉛筆画や木炭画や、木工、竹細工。図工の時間は楽しい時間に変った。
そこで思うのだが、小学校一年時の色覚異常検査を止めて、四年時を初回にしたとすると、一年生から三年生迄の間色覚異常の子供は一般の子供と同一の色覚を強制される事が続く事となり、自他共に正しい知識が育たぬ儘時が経ってしまう。それよりも、一日も早く色覚の異常という事項がある事、それに対する正しい理解と措置を自他共に取る事の必要を知る事が大切だと思う。
(『さわやかパイプのけむり』より「微温湯(ぬるまゆ)」 團伊玖磨〔だんいくま〕)
――引用終わり
*************
もし、このような状況になれば当然、子どもの心は深く傷つき、大きなストレスの中で生活していかねばならなくなります。そのような辛い経験を子どもにさせないためには、入学前から、学校側にあらかじめわが子に色覚異常があるということを伝え、配慮してもらう必要があるでしょう。
もし子どもの描く絵や、色に対する言葉の選び方などに違和感を持ったなら、できる限り早く眼科を受診し、専門医に相談することをおすすめします。また、教員も、色覚異常に対する知識をもち、安易なレッテルを貼ってしまわないように心がけるべきです。
市川 一夫
日本眼科学会認定専門医・認定指導医、医学博士
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】