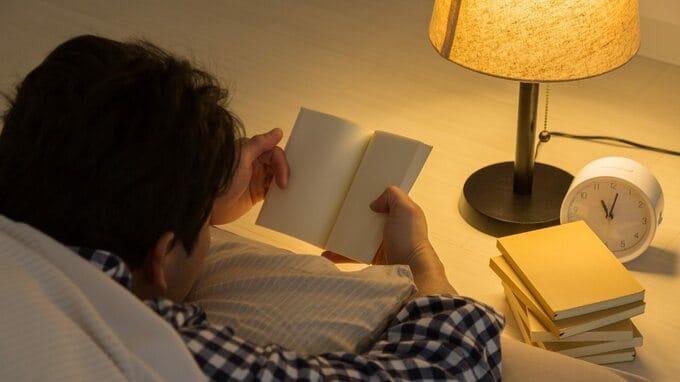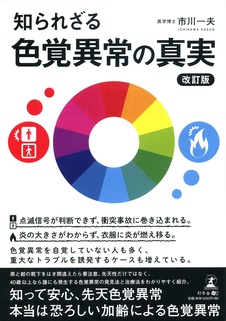色覚異常を早期発見するほど、早期に「補助」できる
私が何度も色覚異常の早期発見の大切さを説明するのは、最近、様々な先天色覚異常に対して、補助手段を使って色を判別しようという試みが数々行われてきているからです。
補助手段として代表的なのは、色がついたフィルターを使うことです。色覚異常のほとんどを占める、条件によって赤と緑の見分けがつきにくい「赤緑色覚異常」である場合には、赤または緑の色つきメガネをかけることにより、今まで区別できなかった色を区別できるようになることがあります。

たとえば、背景が緑と青緑、そこに描かれている数字が赤と橙、という検査表があったとします。
赤緑異常では、緑と橙や青緑と赤が似て見えるため、数字は読み取れません。しかしこの検査表を、赤い色のついたレンズ越しに見ると、緑や青緑からの光が赤いレンズを通りづらく、反対に赤と橙からの光は赤いレンズを通りやすいため、結果として、暗い背景の中に明るい数字が浮かび上がって見えるようになるのです。ちなみに緑のレンズを使うと、これとはまったく逆に、背景は明るく、数字が暗くなります。
こうして、色相を捉えるのではなく色つきレンズを使って明暗の差を作り出すことによって判断するという方法は、限定的ながら活用できることがあります。
ベルトコンベヤーに乗って流れてくる製品の中から赤い色のものを見つけるような時には、より明るく見えるものを探し出せばいいことになります。
このような補助法は、万能とまではいきませんが、特定の条件下では有効に活用できます。職種やライフスタイルのどこかで活用できるかどうか、検討してください。
「色覚異常を補う技術」がぞくぞくと開発中
世の中もまた、次第に色覚異常の人が過ごしやすい方向に変わってきています。色覚異常を補う技術が現在、ぞくぞくと開発されているのです。
最も顕著といえるのが、ウェブデザインの領域です。たとえば、ウェブ技術に関わりの深い企業、大学・研究所、個人などで構成され、ウェブで利用される技術の標準化を進める国際的な非営利団体である「W3C」では、ウェブデザインにおいて色覚異常の人にとって読みづらくなるような特定の色使いを避けることが推奨されています。
また、前景色と背景色の色や明度の差を一定以上にするよう、ガイドラインも示しています。これらの対応を行うことで、色覚異常があっても読みやすいウェブサイト構築を目指しているのです。
ちなみに私も現在、色覚異常の人にとって見やすいパソコンのディスプレー開発に携わっています【図表】。ディスプレーの色変換によって、色覚異常者に見やすい色になるため、普及すればさらにパソコンが扱いやすくなるはずです。しかし、先天色覚異常の人に見やすい色は後天色覚異常の人には見えにくくなってしまうことがあります。そのため、あくまでも個人用のディスプレーに限られます。

色だけでなく「形」や「サイズ」で区別する工夫
最近は、色覚正常者と色覚異常者も識別しやすいようにユニバーサルカラーデザインという考え方があるのですが、先天色覚異常と後天色覚異常、正常者では見えにくさが異なるため、すべてを色で区別しようとするのは危険です。
先天色覚異常を重視し、先天色覚異常の方に見やすい色づかいをすると、逆に後天色覚異常や正常の人にとっては見にくくなってしまうからです。信号や標識は、色だけでの区別を避けるべきなのです(⇒【画像:色覚異常がある人に「信号の色」はどう見えるのか?】)。
たとえば信号灯ですが、赤信号のところにピンク色で「×」という印を入れ、色覚異常の人に配慮された信号灯が、2012年には東京や福岡で試験設置されています。信号灯は、LED化の影響で色覚異常の人にとって以前より色の判別がしにくくなったとされていましたが、これが普及すれば、見間違いは一気に減るでしょう。ちなみに、先天色覚異常の頻度が高いヨーロッパでは信号の色によって大きさを変えている信号灯も散見されます。
また充電器の「充電中」「満タン」を示すライトなど、赤と緑のLEDが判断基準となるような電子機器も、色覚異常の人にとっては見づらいものでしたが、青色のLEDが開発されたことにより、青と赤、青と茶色の組み合わせの2色LEDも製品化されています。
このような動きは今後さらに加速し、色覚異常の人でもストレスなく暮らせる世の中になっていくはずです。
市川 一夫
日本眼科学会認定専門医・認定指導医、医学博士
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】