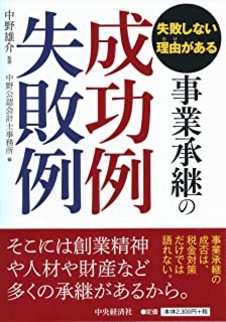公認会計士からのアドバイス4つ
●親族というだけで身内を入社させるべきでない
みやび印刷では、お互いに議論ができない状態が続いたことで、正常な方向への経営改革ができないまま、事業を衰退させていくこととなりました。経営へ貢献できていない身内も会社に入っており、昔の最盛期に稼いだ遺産を食い潰しているのが現状です。身内贔屓や家と会社の公私混同が、他の従業員のモチベーションを下げてしまう可能性も否定できないでしょう。
また3兄弟のうち上の2人は引退した形をとっているとはいえ、まだ、事業経営に目を光らせています。その重しがなくなった時、会社に在籍する3人の子どもたちが自分の領分を守り、協力して会社のために尽くしてくれるか疑問でもあります。早く自立を促すべきです。
●兄弟経営の気遣い
経営者は、業界内外の動きにアンテナを張り巡らせ、事業の拡大・縮小・新規事業の可能性などを常に模索し続けなければなりません。本来は、経営の成果・実績に対して厳格でなければなりませんが、従業員を甘やかすことと、育てることとは別です。
また、父から引き継いだ従業員を自分の代でリストラはしたくないとか、情に流されるのでは変革期を乗り切れません。兄弟がそれぞれ牽制し合い、衝突を避け遠慮し続けたことで、中・長期の経営判断を後回しにしてしまい、先細りの事業を食い止めることができなかったのも事実です。
●会社経営の魅力
現経営者の子の親族承継は、後継者が早期に決まり、十分な時間をかけて徐々に事業承継が実行しやすい利点があります。事業承継の準備期間も柔軟に対応でき、財産や株式を容易に移転できるため、所有と経営の一体的な承継が実行できるでしょう。
ただ、現状はリスクの少ない安定した生活を望んだり、必要以上に事業の将来性に不安を抱いたりして家業を継ぎたくない子が増え、親族内承継が減る傾向にあります。
現経営者は、ただ財産や株式を移転させたのみで事業承継を完了させたというのではなく、事業を好転させ、事業としての魅力を向上させることで、事業承継の不安を後継者から取り除くことも求められています。自分の意思決定が経営に直結し、大きな影響を与えるため、経営に対し強いプレッシャーを感じることもあります。
一方で、多くの困難に立ち向かい、従業員とともに乗り越えながら、さらに会社を発展させていく喜びもそこにはあるのです。
●双頭体制、三頭体制の回避
過去の企業の倒産事例にもあるように、兄弟経営、家族経営において、絶対的な権限を持つ1人のリーダー、代表者の独断、独善的な経営が、企業の崩壊へと繫がり、世間の注目を集めて批判にさらされたケースがままあります。そのようなケースを見るにつけ、権力・権限を分散させ、相互に補完や牽制を働かせ、チェック機能を果たすことで健全な経営を図ることも大切なことを痛感します。
一方で、オーナー企業・中小企業の良さは、意思決定の早さと機動的な経営にあります。双頭体制、三頭体制になると、その良さがなくなるケースが多く、ひどい場合には、意思決定ができずにデッドロック状態に陥ってしまいます。オーナー企業の場合は、意思決定者を集約しつつも、バランス良く牽制する体制が効果的で、なによりも、そのことをオーナー自身が自覚することが重要です。
中野公認会計士事務所
※本記事の事例に登場する名前はすべて仮名で、個人が特定されないよう内容に一部変更を加えております。
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】