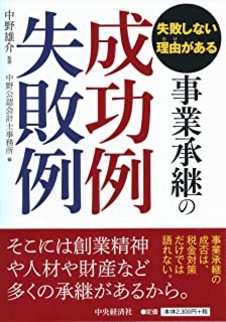自社株式が「分散」していることで生じるデメリット
自社株式が分散する理由として、みやび印刷のように経営に対する責任の担保や相続税対策による場合もありますが、複数の仲間で共同経営として創業し、その後、相続で株式が分散したりするケースもあります。また、旧商法では株式会社設立の際に7名以上の発起人が必要であり、親族や従業員に名義だけを借りて会社を設立するケースもあります。
名義人に相続が起こった場合、実際に名義貸与を証明できる資料がなければ、相続人が相続財産であると主張した場合に、株式は名義人の相続人のものになってしまいます。
自社株式が分散していると、株式買取りの問題だけでなく、相続等で株主が変わり、突然物言う株主が出現する恐れもあります。株主総会の招集請求権等の少数株主の権利も、決して軽視すべきではありません。
分散株式は、計画的に株主間あるいは会社が株式を買い取り、名義株があれば整理をしておくことが肝要です。
長男の社長就任後は業績が年々下がり、資金繰りに苦慮
大一郎が社長に就任してからは、父の龍一が危惧していたとおり、印刷業界の市場が年々縮小していきました。
大一郎は父が大きくした会社を、その延長線上で何とか維持したいと考えており、今まで会社を支えてくれた従業員で変革を図るべく指示を出しますが、残念ながら昔の印刷業しか知らないメンバーでは、大きな荒波の中にある会社を変革することはできず、年々業績は下がる一方でした。
昭二郎は、印刷業界の大激動時にあって、このままではみやび印刷も大打撃を受けるだろうと予測しており、新規事業の開拓や新分野への進出は必須と考えていました。
本来であれば、そのために大幅に人材の刷新を図り、時代に対応すべきでしたが、会社を大きくしてくれた既存のメンバーを大切にする大一郎の方針に反対することができませんでした。
大一郎が社長に就任して10年経った頃、とうとうみやび印刷は資金繰りに窮することになりました。
金融機関から経営改善計画を求められ、社長交代へ
しかし、既存路線のままでは会社の業績が上向くことはなく、だらだらと5年が経過しました。その間、昭二郎は、大一郎に会社の財務状態については報告するものの、自身の進言でリストラが実行されることは忍びなく、また、弟から兄へ意見することも憚られ、会社の将来について兄弟間で真剣に議論することはありませんでした。
5年経過した時に担保資産も底をつき、金融機関からは抜本的な経営改善計画を求められ、ようやく外部専門家とともに抜本的な改革に取り組むことになりました。金融機関からは、経営責任をとって大一郎社長の役員退任、社長交代を要求され、社長には昭二郎が就くことになりました。
新社長の昭二郎はリストラを実施して、財務体質改善へ
大一郎から社長を引き継いだ昭二郎は、今ある経営資源をどのように配分していくかを考え、まずは、毎期赤字の続いていた事業構造を再生させることが急務であると考えました。
将来に事業を継続させることを第1に、余剰人員の徹底的なリストラを断行し、事業構造改革を実行しました。昭二郎は根気強く1人ずつ面談をして、相応の条件を提示していきました。その結果、リストラによる従業員の動揺や混乱を最低限に抑えることができ、組織を再構築しました。
90人近くいた従業員を、20人程度に絞り込む人員整理を断行したことで、今の経営状況が続いても、この先10年は現在の財産で乗り切れる財務体質を作り上げたのですが、衰退していく印刷業に対し、抜本的な打開策を見出せない状態が続きました。