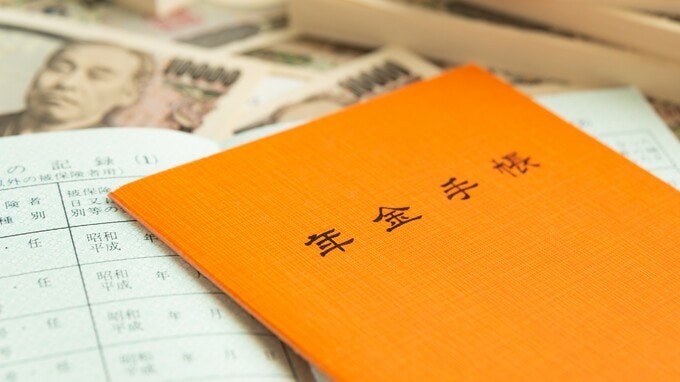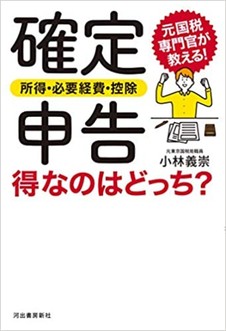「iDeCo」と「小規模企業共済」得なのは?
正解:資金繰りの悪化に強い「小規模企業共済」のほうが安心
この項目は、フリーランスなど、個人事業主の方に向けたものです。
個人事業主にとって、老後資金の準備は欠かせません。なぜなら、将来受け取れる年金が国民年金の老齢基礎年金のみとなってしまう可能性があるからです。
厚生労働省が公開している「平成29年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、たとえ国民年金保険料を満額納めていても、国民年金の平均月額は5万5000円しかないそうです。これでは、どう考えても生活には不足します。

サラリーマンであれば、国民年金に加えて厚生年金(公務員は共済年金)を受け取ることができます。厚生労働省の同資料によると、厚生年金の月額平均支給額は約15万円ですから、老後資金の準備においては、サラリーマンにくらべて、個人事業主はかなり不利と考えるべきでしょう。
ただ、その代わりに個人事業主には老後資金を貯めるうえで使える優遇措置が複数用意されています。代表的なものが、「小規模企業共済」「国民年金基金」「個人型確定拠出年金(iDeCo)」の3つです。
そこで、ここでは「iDeCo」と「小規模企業共済」を比較してみたいと思います。
両者の節税効果はひじょうに似ています。メリットは、「掛金の支払い時」、そして「将来の受取時」にそれぞれ用意されています。
まず支払い時について。国民年金基金の掛金は社会保険料控除として、小規模企業共済の掛金は小規模企業共済等掛金控除として、全額が所得控除になります。名称こそ異なりますが、節税効果としてはまったく同じです。
たとえば、年間の事業所得500万円の人が、その年にiDeCoの掛金を10万円、小規模企業共済の掛金を60万円支払っていたとしたら、所得500万円から、社会保険料控除10万円と小規模企業共済等掛金控除60万円を両方引くことができます。
受取時については、iDeCoも小規模企業共済も、分割(年金)もしくは一括で支払われます。このとき、年金で受け取れば「公的年金等控除」を、一時金であれば「退職所得控除」を受けることができ、やはり節税になります。