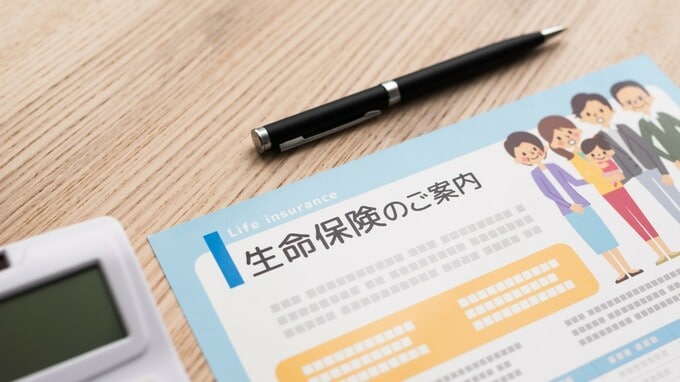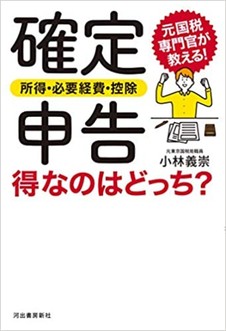夫の死亡保険料「妻が払う」「夫が払う」どっち?
正解:満期保険料の扱いを考えると、「夫が払う」が正しい
所得控除は名義ではなく、じっさいに支払った人につけることができると説明しました。そのため、所得控除に関する支払いは、所得税が多くかかる人がおこなうのが有効ということも理解できたと思います。
ただ、生命保険に関しては、注意が必要です。というのも、「誰が保険料を負担したか」によって、思いもよらない税金がかかる可能性があるからです。

じつは生命保険にまつわる税のしくみはややこしく、国税庁も「確定申告の際に誤りの多い事例」としてホームページで公表しているくらいです。
生命保険の扱いがややこしいのは、「保険料を負担する人」と「保険金受取人」の関係によって扱いが変わってくるからです。一方、「保険契約者」の名義は関係ないので混乱してしまいます。
一般的に多いのは、「保険料負担者と保険金受取人が同じ人」という場合でしょう。「妻が亡くなったら、夫が保険金を受け取る」という保険で、保険料を夫が負担しているようなケースです。
この場合、満期保険金を受け取った本人の一時所得として、確定申告が必要となります。受け取った金額から、必要経費として払い込んだ保険料を引きます。そして、一時所得には「特別控除50万円を引いて、2分の1にする」というルールがあるので、思ったほどは税金がかからないはずです。