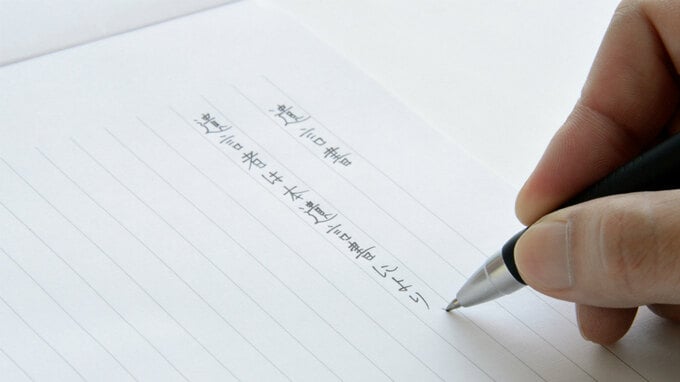遺言者の意思を尊重して、可能な限り有効とすべき
このような事案において、裁判所は以下のように述べて遺言の効力を認める判断をしました。
まず、遺言の解釈の一般論として
「遺言の解釈に当たっては、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきである」
「可能な限りこれを有効となるように解釈することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提にしながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯及びその置かれた状況等を考慮することも許されるものというべきである。」
と述べ、遺言を可能な限り有効とする方向で検討すべきとの解釈指針を示しています。これを前提とした上で、本件については、
「本件遺言書の文言全体の趣旨及び同遺言書作成時の遺言者の置かれた状況からすると、同人としては、自らの遺産を法定相続人に取得させず、これをすべて公益目的のために役立てたいという意思を有していたことが明らかである。」
「そして、本件遺言書において、あえて遺産を「公共に寄與する」として、遺産の帰属すべき主体を明示することなく、遺産が公共のために利用されるべき旨の文言を用いていることからすると、本件遺言は、右目的を達成することのできる団体等(原判決の挙げる国・地方公共団体をその典型とし、民法34条に基づく公益法人あるいは特別法に基づく学校法人、社会福祉法人等をも含む。)にその遺産の全部を包括遺贈する趣旨であると解するのが相当である。」
「また、本件遺言に先立ち、本件遺言執行者指定の遺言書を作成してこれを被上告人に託した上、本件遺言のために被上告人に再度の来宅を求めたという前示の経緯をも併せ考慮すると、本件遺言執行者指定の遺言及びこれを前提にした本件遺言は、遺言執行者に指定した被上告人に右団体等の中から受遺者として特定のものを選定することをゆだねる趣旨を含むものと解するのが相当である。」
と判示して、「受遺者の特定にも欠けるところはない。」と結論付けました。
このように、裁判所は、遺言書のなかで贈与先(寄付先)が具体的に特定はされていなかったものの、「どこに寄付するかは遺言執行者にゆだねる趣旨である」との解釈をして、この遺言を有効と判断しました。