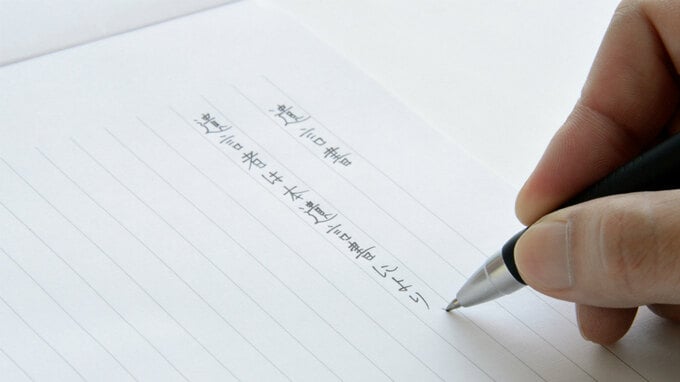「有効な遺言書」を作成するために重要なこと
家族がいない人、もしくは家族と疎遠となっている人で、もし遺言書などを遺さなかった場合には、その遺産は
・家族(相続人)がいなければ、遺産は国庫に帰属する
・家族(相続人)がいる場合は、どんなに疎遠であってもその家族(相続人)に帰属する
ということになります。このような人の場合、自分の死後に自己の遺産を、家族以外のお世話になった人や、公的な機関に贈与または寄付をしたいと考えることも多々あると思います。
そのような場合は、遺言書で、しっかりとその贈与または寄付の希望を遺しておく必要があります。
遺言書を作成するにあたっては、有効にするためには法律の方式にしっかりと従って書くことが求められます。
公正証書遺言で作成する場合には公証人のチェックがされますので、この方式が守られておらず無効になるケースというのは稀ですが、自分で書く自筆証書遺言の場合、方式が守られておらず無効となってしまうこともありますので、注意が必要です。

贈与、寄付先が特定されていない場合は…
特に、自分の財産を相続人以外の第三者に贈与もしくは寄付したい場合に問題となるのは、「贈与または寄付先が特定されていない」という場合です。
個人であれば氏名と住所はしっかりと特定し、団体であれば法人名やその本店所在地などの住所でしっかりと特定できるだけの記載を遺言書に書いておかなければ、特定不十分として贈与または寄付が効力を生じないという事態になってしまう場合もあります。
この点を巡って問題となったのが、最高裁裁判所平成5年1月19日判決の事例です。
「一、発喪不要。二、遺産は一切の相続を排除し、三、全部を公共に寄与する。」
と記載して遺して知人を遺言執行者として託していました。そして被相続人の死後に、この遺言の効力が問題となりました。
家族側(相続人側)は、「公共に寄付する」だけでは、寄付先が特定されていないから無効だと主張し、遺言を託された遺言執行者は「相続を排除し」とも書かれており、公共的な機関に寄付するという意思明確だと主張しました。