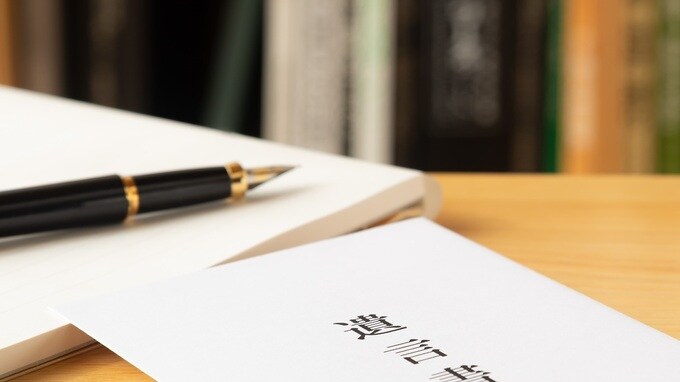母親違いの妹に「ひとりだけいい思いをして…」
今回の相談者は80代男性の根本さんです。同居している長女の真由美さんに自宅財産を残す方法をアドバイスしてほしいと、筆者の事務所を訪れました。
根本さんは再婚しており、長女の真由美さんは後妻との間に生まれた子どもです。先妻との間には2人の息子がいます。先妻は、息子たちが中学生・高校生のころ、急病で亡くなりました。その2年後、根本さんは勤務先の部下と再婚し、真由美さんに恵まれました。
長男・次男は大学を卒業するとすぐに家を出て独立。ともに20代半ばで大学の同窓生と結婚しました。いまは神奈川県や埼玉県に自宅を構えて家族で生活しています。
根本さんは後妻と仲睦まじく暮らしていましたが、3年前、後妻に深刻な病気が発覚しました。ちょうどそのころ、娘の真由美さんは離婚が決まりました。そのため、根本さんは真由美さんとその子ども2人を自宅に呼び寄せ、同居することにしたのです。真由美さんはかいがいしく母親の看護を行いましたが、残念ながら回復せず、母親は帰らぬ人となってしまいました。真由美さんは母親の死後も根本さんと同居を続け、小さな会社の事務員を続けながら、子どもたちの面倒を見つつ、根本さんの身の回りの世話もしてくれています。
先妻の子どもである息子2人と、後妻、そして後妻の子である真由美さんは、とくに親密な関係ではありませんでしたが、かといってギクシャクするわけでもなく、根本さんは家族関係に不安を感じたことはありませんでした。しかし、後妻の葬儀の際、息子たちが「真由美ばかりがいい思いをしている」と不満そうに話しているのを聞いてしまい、このままにしていては、相続の際に娘が生活基盤を失うことになるかもしれないと焦りを覚えたそうです。
「確かに中高生だった息子たちは、私がすぐ再婚に踏み切ったことに不満だったかもしれません。ですが、それまで仕事一辺倒だった私は、生活すべてを切り回してくれた妻を失い、途方にくれてしまったのです。事情を知る相手と再婚できたからこそ、その後の生活も維持できたのです」
「息子たちは、さっさと相手を見つけて結婚してしまい、私のところには寄りつきません。相手の実家とばかり交流していて、たまに連絡があると思えば、孫の入学祝いや卒業祝い、新築祝いなどお金のかかる話ばかりで…。それなのに、私も妻もお祝いの席に呼ばれたことすらないのですよ。先日など、次男から急にお金を用立ててほしいといわれ、一体なにごとかと思えば、奥さんのご親族たちとの豪華温泉旅行の計画があるとか」
「後妻や年の離れた妹がいる家には足を運びにくいだろうと思って、だまって要求はかなえていましたが、そこまでしてやったのに、私や妻の面倒を見てくれた真由美にまで不満を持っていたなんて…」
根本さんの表情には悲しみがにじんで見えました。
遺言作成者:父親 根本博(相談者) 80代
推定相続人:長女 真由美 40代(後妻の子)
長男 裕一 50代、次男 武史 50代(先妻の子)
相続財産 :自宅、アパート、預貯金