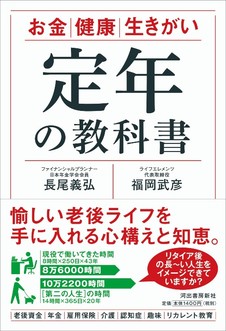老後生活の破綻するどうかは定年後の収支バランス
最初に、老後の不安で第1位になっている「お金」についてを考えていくことにします。老後生活を豊かに過ごすためには、この「お金」の問題をどうしても解決する必要があります。なんとかなるなんて目を背けていても、逃げられません。
また、先延ばしにすると、解決できる選択肢を狭める結果になります。まずは、ご自分の家計がどんな状態なのか、現状を把握することが対策の第一歩になるのです。
2019年、金融庁の金融審議会市場ワーキング・グループの報告書が発端となり、「老後資金2000万円問題」が話題になりました。これをきっかけとして、老後資金について考える人が多くなりました。この問題がある意味で、いい意識チェンジになったとは思います。

老後になって、2000万円不足するというのは、総務省統計局の家計調査報告から導き出された数字です。高齢夫婦無職世帯の家計収支の2017年のデータでは、収入が20万9198円で、支出(非消費も含む)が26万3717円となっています。毎月の不足分は5万4519円です。この不足分を30年間埋めるために必要なお金が、約2000万円なのです。
数字が、老後に2000万円が不足するという根拠になっています。
ただし、2000万円はあくまでも平均的な数字です。また、持ち家の人が主なデータなので、賃貸の人には当てはまりません。
老後生活が豊かになるのは「老後資金の金額」ではなく「収支バランス」だ
では、老後に必要なお金はいったいいくらなのでしょう。答えは、人それぞれです。答えになっていないと怒らないでくださいね。必要額を計算する方法が、ちゃんとあります。ポイントは定年後の収支バランスです。収支バランスがわかれば、老後資金の額もわかります。
毎月の不足分を補うのが老後資金の大きな役割です。つまり、足りない金額×寿命が老後資金となります。
もっとも、寿命は誰にもわかりませんので、平均寿命で計算するしかありません。とはいえ、途中で資金が枯渇しては困りますから、長めの年数で計算しましょう。まずは、95歳を目安にしてください。
65歳まで働くとすると、95歳までは30年間です。
老後資金=毎月の不足分×12か月×30年
という計算式になります。
平均額ではなく、ご自身の不足額を入れることで、自分の老後資金がわかるわけです。