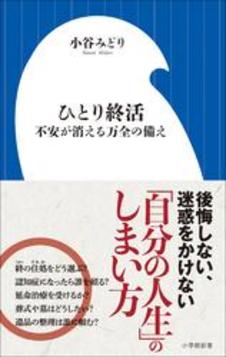85歳以上の女性、5人に1人は5年前と別の場所に居住
地方に住む高齢の親を、子どもが住んでいる都市部に呼び寄せるという傾向は1990年代以降、顕著になっています。離れて暮らす親に老いを感じはじめると、「そろそろ同居をしたほうがいいのだろうか」と考える子どもは多いはずです。転職や定年退職を機に、子ども世帯がUターンして、親と同居をするケースもありますが、子どもが仕事や生活環境を変えられなければ、親を呼び寄せて同居をするしかありません。

実際、ひとり暮らしをしている高齢女性の多くには、離れて暮らす子どもがいます。元気なうちはともかく、親に介護が必要になってくると、離れて暮らす子どもも不安です。
国立社会保障・人口問題研究所の「人口移動調査」(
同じ市区町村に住んでいる人は85歳以上では40.5%
5年間で最低1回は転居している計算となります。
住んでいるは35.9%と、男性の47.0%
女性で転居する人が多いのは、夫と死別するなどして単身になり、
場所や施設などに移動するケースが多いからだと考えられます。
年以内に転居した人の理由として、65歳以上では「
理由」を挙げた人の割合が増えてきます。
「呼び寄せ同居」が抱える問題とは?
高齢になって健康に不安を抱える親が、子どもに呼ばれて転居する、いわゆる「呼び寄せ高齢者」がその典型例です。しかし、呼び寄せ同居には問題もあります。健康なうちに転居するならまだしも、健康状態が悪くなってからの新しい環境は、高齢者にとって大きなストレスとなります。呼び寄せる子どもの側も60代ぐらいになっていれば、老親の介護は肉体的に大変です。
自治体によっては、子どもと同居する高齢者には、ホームヘルプサービスなどの生活援助を介護保険の対象外とすることもあります。離れていれば仲良くできても、一緒に暮らすと、些細なことで言い合いになったり、険悪になったりすることもあります。嫁姑問題も起きやすいようです。
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】